社長がティールパラダイムの域に達していて、役員メンバーも社長の方針に賛同してくれている状態。さあ、これからティール組織に変容させるぞ、というときの混乱状況を予想してみます。
非常に聡明で人間味のある社長(=自己のエゴを手放し、「恐れ」が「信頼」に置き換わる境地に達した状態)は、「恐れ」からくる行動である、頭ごなしに社員のミスを責めたり、再発防止のためやみくもに監視体制を強化したりしません。
社員が失敗から学び成長することを願い、社員と話し合い共に組織の改善を行っていきます。こんな最高の社長と役員の指導の下、その組織の社員達はどうなっていくのでしょうか?
普通の組織(オレンジ組織)からティール組織に変容しようとする立ち上げ期に求められる「社員の資質」についての考察です。
5割以上の一般社員はティール組織化に協力的
欧米ではオレンジ組織からティール組織に変容するとき、ティールパラダイムに達している社員は約1割と言われています。
2-6-2の法則から考えて、ティールパラダイムに達していなくても大体理解出来る人も合わせて、上位2割と仮定します。そして、中間の6割の内最低でも半数以上の社員は自分にメリットがあると考え、ティール組織化に賛成します。つまり5割以上の一般社員はティール組織化に利害の点で賛成です。
保守的で真面目な性格の人は最初懐疑的でも途中から賛成派に転向する人もいますが少数です。最初に協力的で学習意欲があったとしても、なかなか身に付かなかったり、やってみて自分には合わないと感じ脱落していく人が多数います。
例えば、50人の社員でティール化を開始すると、40人辞めて入れ替わった頃に組織のしくみがやっと出来上がります。
その後1~2年の運用経験を経て、また40人入れ替わる。最悪の場合2周り入れ替わってやっと組織が安定すると考えます。社員の質がティール組織として望まれる振舞いの期待値以上になるまでは、社員が2周り入れ替わり、辛い時期が続きます。
その間の現場の戦力低下は、「失敗からの貴重な学び」であることには変わりないのですが、会社全体として耐えられるかどうか、は社長の判断に委ねられます。仕組みとして補う方法はいろいろあるのですが、トレードオフで失うものもあります。社員が主体的に試行錯誤するOJTの機会を削ぐことになり、後に社員が伸び悩む原因になります。
この点は「社長がどれだけ社員を信じることができるか?」にかかっており、常に社員を信じる方向に振った対応を心がける必要があります。
軌道に乗ってしまえば、ティール組織は「最高のOJT環境」
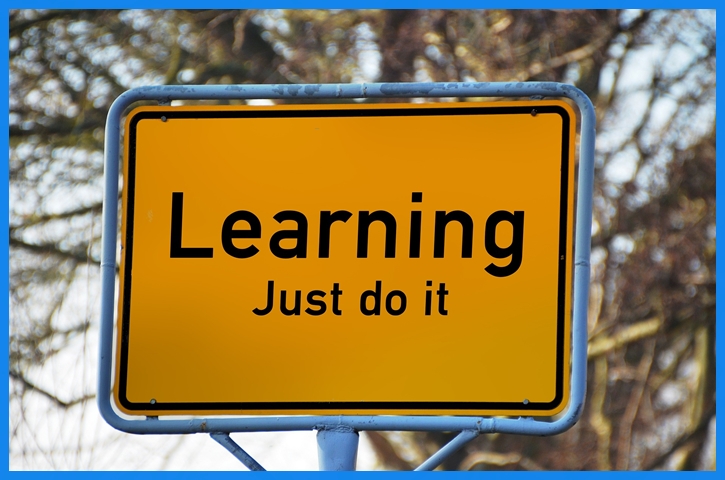
辛い時期を乗り越えて回りだしたティール組織ではどんな日常になるのでしょうか?
ティール組織に属する社員は「組織の力による最高に効果的なOJT」を毎日受けることになり、どんどん主体的に動き出します。よく言われる「経営者目線」で動くようになります。ただ、自由は責任とセットであり、下記のしくみがそれを支えます。
しくみ1:採用時の徹底した話し合いと確認
新規採用される社員は採用前にこの組織に合っているか?やっていく気持ちはあるか?じっくり話し合い合意を得て入社します。
しくみ2:新規入場時の研修
入社後も職場に配置される前に、基礎的な相互コミュニケーション方法を研修からしっかり学びます。絵に描いた餅的理想論でなく、実際に現場で守らないといけないことを教えます。これで最低限のコミュニケーションは取れるようになります。
しくみ3:助言システムで紛争を解決する
上司はいませんが、仕事の妨げになる水準以下の同僚もいません(上記スクリーニングを受けた社員しか残れない)。
同僚にサポートも依頼できますし、専属の「コーチ」もいるので、社員は自分の仕事に集中し、水準以上の質の仕事ができます。
「完全に個人で周囲と業務連携して行動」 or 「2~10人のチームで行動」はその会社のバリューチェーン等により変わってきます。連携して仕事を行う時の意見の相違や紛争は、「助言プロセス」を使って解決します。
社員を信じ、全員が「自由と責任」の意味を理解している社員たちだと信じても、ごくまれに不祥事は起きるとティール組織のパイオニア企業は述べています。ただその割合は、オレンジ組織の監視体制下で起きる問題よりはるかに少ないとも報告されています。
問題は「過渡期の水準に達していない社員」をどこまで信用するか?
社員の育成に最適なのは現場で自ら試行錯誤し経験から学ぶことです。
それは分かっているけど、納期やコスト削減からギリギリのリソースで、出来る人の手足となって使い続けることになりがちです。適切な指導やコーチによるサポートがあれば十分戦力になる人が、パワハラ等で辞めていく。
そんなオレンジ組織の現状から一旦離れる必要があるので、再度ティールパラダイムの価値観を説明します。
まず、下記は「ティール組織」からの引用です。「従業員」というのは「ある一定のティールパラダイムの価値観のスクリーニング」を受けた人でなく、ごく普通のオレンジパラダイムの人達と想像します。
“ダグラス・マクレガーが提唱したX理論とY理論で説明すると、経営者は従業員について次の二つのうちどちらかの見方をしているという。
1従業員は本来怠け者で、なるべくなら仕事をサボりたいものだ(X理論)。
2労働者は意欲的で、自発的で、自制心を発揮できる(Y理論)。
どちらが真実でしょうか?
マクレガーは何度も検証を重ねたうえで、ある重要な見解に達した──どちらも正しいというのである。
人々を不信の目で見て(X理論)、あらゆる種類の命令、規則、罰則で従わせると、彼らは制度を出し抜こうとするので、あなたは自分の考え方が正しかったと感じるだろう。
信頼をもって接すると(Y理論)、責任感ある態度でその信頼に応えようとするはずだ。
すると、自分の立てた前提が有効だったと感じるだろう。これを発達心理学の観点から説明しよう。
アンバー/オレンジ色の強い組織構造と組織文化をつくり上げると、人々はアンバー/オレンジ式の反応をするようになる。ティール色の十分強い組織にすると、人々もそのようにふるまい始めるのだ。
英治出版 「テール組織」暗黙の前提を明らかにする p178 フレデリック・ラルー著”
つまり、「どんな従業員でも、最後まで信じ続けるべき」と読み取れます。
日本のティール組織のパイオニア企業、日本レーザーの近藤社長は、「会社の理念に賛同し尽くしてくれる社員が会社に残りたいと望む限り、何があってもリストラはしない。本人の希望を通してあげる。」と言われています。近藤社長のこの考えこそ、まさにティールパラダイムそのものです。
日本レーザーのティール化への道のりは、いきなりティール組織の形はとらず、段階を経ています。その理由は、まだ社員の質を含む様々な環境が整ってなかったからのようです。
「社員を信じること」と「現時点の社員の質」は分けて判断され、ワンマン体制から段階を経て時間をかけて変容されています。「社員が働く環境の改善」→「社員のモチベーション向上」→「社員の質向上」→「ティール化(予測)」と進んできています。
「ワンマン体制」イコール「社員がやりたい放題に勝手なことばかりする体制」ばかりではないと思います。役員や社員の賛同を得られるのなら、「迅速に組織変更出来る」メリットを生かして、新しいしくみを朝令暮改で試しながらどんどん修正していけばいいのです
ティール組織で求められる社員の資質とは?
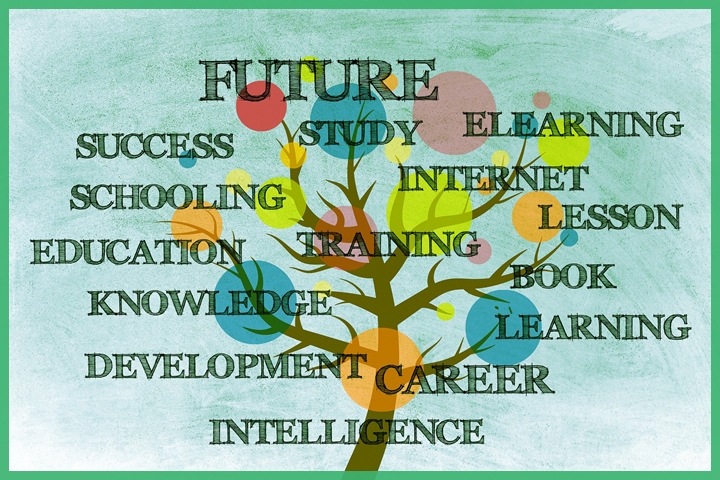
従来の組織(オレンジ組織)でも、コミュニケーション力や自制心、倫理感、道徳観は必要です。
しかし、何よりも利益と効率化を最優先するオレンジ組織の価値観においては、目先の利益のため優先度を何段階も落とされるのが日常です。
管理職も個人的な感情を殺して役職に合わせた仮面を被り行動することが求められているので、同僚同志で競争を煽る環境である限り、弱者へのハラスメントはなくなりません。
イジメに黙って耐え抜き、階級が上がると同僚や上司の不正や周囲の違和感に目をつぶり平静を保つ。つまり、常に「自分の感情をごまかせる能力」「当たり障りなく周囲と付き合える能力」が要求されます。
ティール組織では、自分自身の価値観と指針に従う
組織全体が進む方向を見定め、自分のやるべきことを決めます。自分に正直に生きるということは、相手が間違っていると感じたら黙認せず、話し合います。論争し言い負かし、自分に従わせるのではなく、自然に、冷静に相手を尊重し妥協点を探すのです。
周りの人達の賛同を得たいと思い、好感を持たれる行動を取りたければ取ればいい。自分が正しいと信じることを行い周囲から賛同を得られなければ、自分を省みて正すべき点は正せばいい。
2人で話して解決しない場合は、同僚やコーチにサポートを頼み、まだ収まらない場合は役員や社長まで立ち会ってもらいます。ティール組織とはこういうものです。自由を得るには責任が付いて回ります。うやむやにしたり、都合の良い部分だけ取ることは出来ません。
こういった紛争時の明解な解決方法があって初めてティール組織独特の個人の自由な創造性が生まれてきます。ローコンテクスト文化の欧米なら想像出来ますが、ハイコンテクスト文化の日本人にはハードルが高いかもしれません。自分で積極的に解決するより、波風立てたくないから多少は我慢できる。自分さえ被害被ってなければいい。そう考える日本人は多いかもしれません。そう考える人が多い状態の組織にはやはり最初は社長ワンマン体制が合うでしょう。
シンプルに言うと「自主性」と「責任感」
ティール組織のパイオニア企業の1つ、アメリカのモーニング・スター社は、最初の従業員たちとどうやって一緒に働きたいかを話し合い、下記の二つの原則に従ってあらゆる経営慣行を決めました。
1. 個人は決してほかの人に何かを強制してはいけない
2. それぞれの約束を守ること
非常にシンプルですね。
1について:強制されない。強制しない。自分で考える。
「強制しない」という言葉の意味には、「嫌なことはしなくてもいい」という意味もあります。「嫌な人とは仕事しない。同じチームなら別のチームに行く。」ことも可能です。人の道を外れた行動を取る人間は容赦なく干されます。
2について:自分の行動に責任を取ること。
会社は社員を信じ、大切にする。だけど、もし約束を破った場合(不正を働く等)はオレンジ組織より厳しい処罰があるはずです。
「倫理観」や「奉仕精神」は必須のコンピテンシーではありません
ティール組織では、そのような振る舞いも強制しないし、そもそも必要ありません。組織の力で全員がそのように自然に振舞える環境だからです。
周囲の人から嫌われるより、好かれる行動を取る方が自分の価値観や生き方に合っている人が自然に残っていきます。それが本来の人の感情に沿った自然で合理的な振る舞いだからです。
まとめ
ティール組織は最高に利益の上がる合理的な組織マネジメント方法です。しかし、それは利益が目的ではなく、各自が自分の指針に沿って自然に合理的に振舞うことの結果として利益が出るのです。
同じことが個人の資質にも言えます。「倫理観」や「奉仕精神」や「創造的発想」が目的ではなく、結果として行動やコンピテンシーに現れるのです。
求められる資質は「他の人に強制しないこと」「約束を守れること」の2つだけと、非常にシンプルです。この2つを守れる人がティール組織で日々OJTを付けながら働くことで、結果として素晴らしいコンピテンシーを発揮するようになるのです。もちろん「経営者目線」で動けるようになります。
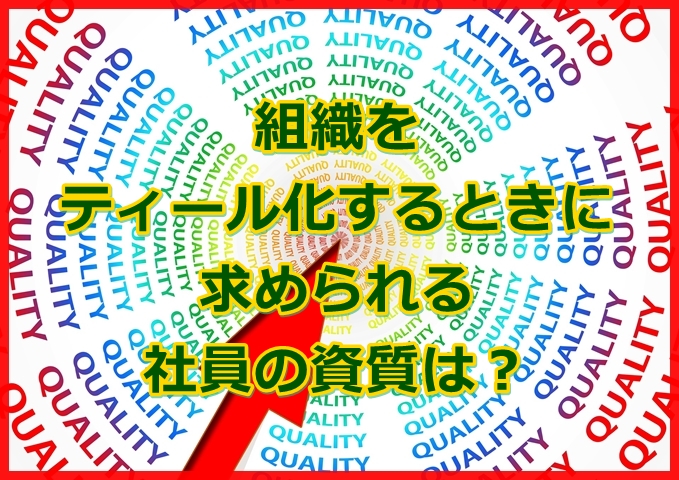


コメント