 ティール組織
ティール組織 中間管理職が組織改革をしようとするとき #2
テーマ「中間管理職の有志が集まって組織改革を草の根的に行うにはどうすればいいか」の#2になります。残念ながら中間管理職に出来ることはほとんどありません。ただマネジメントやリーダーシップを勉強し、日々の行動に取り入れることで少しずつ変えていけることはあります。そのヒントになるものをご説明いたします。
 ティール組織
ティール組織  組織改革
組織改革  マネジメント
マネジメント  ティール組織
ティール組織 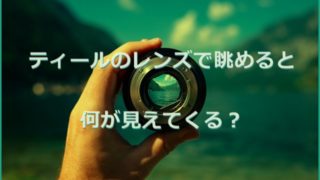 ティール組織
ティール組織  ティール組織
ティール組織  ティール組織
ティール組織  ティール組織
ティール組織 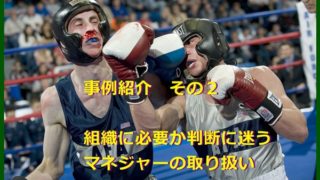 事例紹介
事例紹介  マネジメント
マネジメント