中間管理職のマネジメント力低下
よく言われていることですが、中間管理職が機能しなくなっています。具体的にどんな問題があるのでしょうか。
部下を指導する力がない
世の中の環境の変化が激しくなり、過去の経験やマネジメント方法は通用しなくなっています。以前は部下から業務の概要を聞くだけで指示や指導をすることができたのですが、今は以前より専門性やスピードが要求され、優秀な部下の場合は仕事の相談に乗ってやれず、雑用や他部署への根回し程度のサポートしかできない。状況が良く分からないまま口出しすると部下に迷惑がられるだけです。出来ない部下の場合も適切な指導が出来ず、叱咤によるパワハラやモチベーション低下を招くことになる。何とかしないといけないと考えコミュニケーションの改善を図ろうと思っても、自己完結型の業務スタイルが一般的になった職場で急に流れを変えることが出来ずに徒労に終わる。
部下の人数が多すぎて面倒見れない
充分なコミュニケーションが取れる部下の人数は7人までです。最近は人員削減で部下が20人以上の場合があるようです。加えてプレイングマネージャとしての役割も課せられると、さらに多忙になっています。一人ひとりの部下がある程度機能する状態まで教育出来ていたらプレイングマネージャとして動けるのですが、部下の指導が必要なときはマネージャに専念したいところです。そういった事情をさらに上の上司である部長/事業部長クラスは全く聞こうとしない/考慮しないのでストレスはさらに蓄積します。
人を育成すること自体に関心がない管理職が増えた
競争に勝ち残り管理職となった者は、昇進や権力に興味はあるが部下の育成指導は全く関心がない。自分の成功体験からの持論を押し付ける。自分より階級が下の人間には関心がないので話を全く聞かない。自分の得意分野だけに線引きした仕事をしたがる。部下の心の痛みを全く想像しない。理解しようとしない。自分にこびへつらう部下には甘いが毅然とした態度の部下には冷たい対応をする。基本的に人と人間的に平等にコミュニケーションすることが出来ない。抽象度の高い言葉で指導したがる(「経営者目線で考えろ!」)。こんな上司に指導されると、部下の気持ちは落ち込み、優秀な人材ほど反発せずにいきなり辞めていく。
問題の解決方法
この問題を解決するには、まず、多忙な中間管理職の業務から「部下の指導育成」の負荷を軽減することが最優先です。現時点で「使えない」社員が多い状況でも、思い切って「管理職を無くし、同じ立場の社員にする」という組織変更を行います。段階的に行う場合は、管理職の数を大きく減らし、実務をやらず「指導」ではなく「コーチ」を担当する役割に回します。「指導、育成」と「評価」を中間管理職のいわいる「プレイングマネジャー」に任せるのは指導する側にも指導される側にもマイナスになります。社員全員が平等に「指導、育成」され、「評価」され、「情報の共有」を出来るようにしくみやルールを変更します。
社員の指導育成
業務内容によりますが、基本は個人でなくチームで仕事を行います。現場で他の社員の細かな行動を見ることで各自が考えて学んで行きます。現場で不足していると感じた知識やスキルを補うためにはチーム内で相談し、チームメンバーが指導する/社内でその分野が得意な社員に指導を依頼する/外部研修を受講する、等の方法を選択します。人事部等の間接部門に研修を企画させるのは止め、現場がすべて行います。
今まで外部研修を受講したあと現場で実践しようとしても、あまりにも理想と現場が乖離し、どこから手を付けていいか困ったことがありませんか?関係者に相談しても適当に対応され、たとえ協力者がいても、あくまで主体的に動くのは自分しかいなかった、そんな経験はありませんか?
何が邪魔していましたか?「情報やノウハウを独り占めして、その力で自分の立場を確立して威張っているジャイアン的社員」、「相手によってコロコロ態度を変える要領の良い(腹黒い)社員」、「悪い人ではないが、長いものには巻かれる日和見社員」そんな人達がほとんどで社員の自発的な行動を促す環境でなかったことが原因ではありませんか?
もしそうなら、それはもう個人のマネジメント力を強化するだけでは無理で、組織的に根本的な改善が必要です。そもそもピラミッド組織では「成果を上げること」「効率化を図ること」を最優先するしくみであり、「自己完結型の仕事」「プレイングマネジャー」「部下を黙らせ指示に従わせる」ことが評価されます。その結果つくり出される人間は、歪み腐っていきます。まだ腐っていない人も、仮面を被り、腐った環境に耐えて暮らします。
この組織環境を改善する方法は別記事でご説明しますが、腐った環境を正すことで、それまであたかも防毒マスクを着けて耐えていた人達は素の自分を出してくれます。無意識に染まっていた多くの人も組織に合った振舞いをし始めます。やがて自由な空気の中で「真面目にコツコツ頑張る社員」、「創造性のある仕事をする社員」が自然に周囲から認められていきます。そして要領が良いだけで薄っぺらな社員は、他人から責められるわけではないのですが勝手に去っていきます。
評価
一例ですが、自己申告し、関係した周囲の人の意見を考慮し、決めていきます。上司の評価がなくなり、昇進昇格の競争が無くなるとのんびりしすぎてパフォーマンスが低下する懸念もあります。何かに追い詰められて行うパフォーマンスと自発的に楽しみながら行うパフォーマンスは本質的に違うものですが、単純に成果を測れるもので比較しても後者が優れています。トラブル発生時は自発的にすべてを自身で責任を持って解決する環境が揃えば、競争ではなく自己の成長の目安として多くの成果を目指すようになります。また、途中経過で見える成果が出ていないもの、定量的な数値で表しにくいものも自分で周囲に説明する機会を設けます。周囲の同僚が認めてくれれば、段々とその「見えにくいが価値のあるもの」、「その現場でしか分からない必要なもの」が見えてきて共有され、その職場の風土となってきます。
情報の共有
今まで管理職だけに提供されていた情報や一般社員より事前に知らされていた情報をすべて一般社員にも公平に提供します。情報操作で優位に立とうとする管理職を無くし、一般社員がオーナーシップを持つようにするためです。また、「承認権限」や「稟議書」のしくみも見直す必要があります。最終的にはすべての社員に平等の権限を持たせることを目標として、組織変更の移行期は、全社員に何をしようとしているのか、最終ゴールと段階的移行内容を共有します。社員を疑い、監視を強化するコストと、社員を信じ、自発的な活動によるメリットを考えてメリットが大きいと考えて進めるべきです。
細かなことですが、普通会社では、組織変更時に本人が知らないうちに新しい組織図や役職が決められ、その空欄に誰を入れるかは経営トップ陣だけで決めています。本人に知らされずに決められ、どんなことを求められているのかも最後まで聞かされない場合があります。社員を機械の部品と捉えるオレンジ組織の特徴ですが、指名された本人は経営陣の細切れの言葉から意図を読み取り苦労しながら周辺組織とのすり合わせを行い自分で細かな所を形にしていきます。上層部に細かな部分を質問しても、「それはお前の仕事だろ。自分で考えろ!」という答えしか返ってこないのは分かり切っていますね。それは当たり前のことで仕方ない、と思った人は部下に同じことをやるのでしょう。
「ピラミッド組織は命令を実行に移すのが早い」という理由はここにあります。断片的な情報を部下に与え、後は任せっきりで、リーダーは「もっと重要なことに集中する」と言います。リーダーにとって「最も重要なこと」はいったい何なんでしょう?
こんなオーナー不在の組織変更を私は何度も見てきました。「お前は言われたことだけをやっておけ!」と言われたら部下はモチベーションが下がり、仮面を被り、本当に言われたことしかやりませんね。
全員で成果を出していく
「社員1人ひとりが特別の精神的武装をせずに、近所のスーパーに買い物に行くように、自然な気持ちで職場に通える。」これから生き残る会社では、そんな職場環境が当たり前になります。
オレンジ組織で自分が勝ち続けられているうちは、満足感が高く生き甲斐を感じられます。世界は自分を中心に回っているように感じ、電話が鳴り自分がいないと仕事が止まってしまう状態が続くと、いつの間にか傲慢になり、仕事が遅い社員、余計なことを言う社員に厳しく当たってしまうようになります。「言われたことも出来ないのか!もういい。自分でやった方が早い」と。
私も経験があります。難しい課題に挑戦し続けそれを乗り越えたとき、達成感があります。次々に上を目指しステップアップするとき「以前はこんなことも乗り越えられたから」と自分に言い聞かせ、どんどん無理をしていきます。部下と接する態度もいつの間にか変わってきていました。時間的にも精神的にも余裕がなくなり、目の前の仕事をこなすことが最優先されます。正直部下のことを気遣う余裕はなかった。そんな状態で部下を評価指導することは困難です。後で経営陣が違う評価を相談なしに付ける場合(その会社では普通のことと受け止められていた)もあり、私は疑問を感じつつ評価していました。個人ではどうすることもできないことが多すぎます。
現状はどうしても特定人材に負荷が集中し、少しきっかけがあれば伸びる人材、得手不得手が極端な人材を活かしきれていません。そして効果的なOJTを受ける機会は少ない。確実に短期成果が出せる人材による組織を作り、効果が下がればまた作り直し、スピード化&効率化で、少ない正規社員と外注会社によるそんなプロジェクト型組織が増えていますが、実務を担当する人間は下請けから孫請けへと移っていき、いつの間にかノウハウを持った人材が流出していきます。
仕事のノウハウや、知識と経験による職人的スキルを可視化、継承することは、短期成果を追求するオレンジ組織では評価されにくく、実施が難しい環境です。グリーン組織やティール組織では情報共有やコーチの存在により、重要な業務と認められ社員の協力も得られます。
「チームで協力したり、お互い助け合うのは当然のこと」という意識が浸透しないと、「自分のノウハウを公開する」気持ちにはなりません。そもそもオレンジ組織では、極論すれば、会社で働く目的が「自分が(一番)評価され富と名声を得ること」です。その結果私欲を満たし、余裕が出たらボランティアを行う感覚で倫理的な行動を取るのです。ティール組織では「互いに助け合うこと」は倫理的な感情から行っているのではありません。会社という組織で動くための「最も合理的なコミュニケーション」と捉えて自然に振舞っているだけなのです。自然に素晴らしい対応が出来る優秀な人材の集団でなく、組織がそうさせるのです。
まとめ
問題を解決するには、多くの要素を同時に改善していく必要があります。また状況に応じて暫定的な環境で一旦馴染むまで変化を止めて待つことも必要になります。
ただ、社員1人ひとりの教育については、組織環境が整えば、その中で試行錯誤の繰り返しを経て、OJTで自然にみんなで成長していきます。人の入れ替わりも当然ありますが。
同じことが中間管理職にも言えます。中間管理職の研修を強化し、個人の実力を上げることよりも、組織という彼らが活動する環境そのものを改善した方が効果的です。部下の育成や評価制度等部分的な組織改善も効果はありますが、「役職や上司や部下といった概念を無くすこと」の方が大きな成果が出ます。
ティール組織にすることが目的ではなく、なぜ、ティール組織は、オレンジ組織の問題の多くを克服しているのか理由を知ることで、今の職場(多くがオレンジ組織)の問題解決のヒントになり、よりスムーズに成果を出せます。
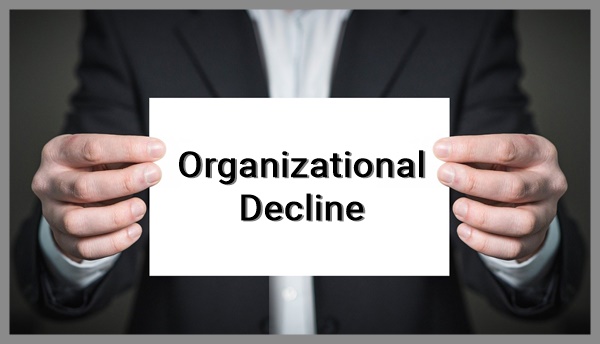


コメント