テイール組織導入方法の過去投稿した4回分を改めて、まとめてみます。
1.ティール組織の前にまずグリーン組織に変える
オレンジ組織の構造のまま、将来ティール組織に変容することを考えながら過渡期の組織形態としてグリーン組織に変えて実務を運行させます。オレンジ組織の横もしくは下にサンプル的にティール組織の部署を作る方法もありますが、それは短期的なOJTとしてとらえた方が良いでしょう。
あくまで実践的な、出来るだけ多くの社員が参加できる形態としてグリーン組織が最適です。なぜ最適かと言うと、グリーン組織は管理職の役職を残したままサーバントリーダーシップを学び、社員に権限を委譲したマネジメントをまなび、社員と一緒に自主経営での社員の行動規範を考えていくのに適しているからです。いきなり理想とするティール組織に移行しようとすると、細かな部分での最適化や個々人のコミュニケーションスキルが追い付いていかず、頭で概要をイメージ出来ても現在進行中の実務への対応で行き詰まり、最悪はバラバラになってしまいます。
運用状態をシミュレーションするには、出来るだけ多くの社員や第一線の人材が参加し、現在進行中の主要業務を扱わないと意味がありません。そのためにもオレンジ組織ベースで始めることはリスクを軽減できますし、ティール組織への学習も平行して行えるからです。
まずはその会社の環境に合ったティール化に留めておき、マネジャーを残し上意下達の部分もマイナス要素に気を付けて運用すれば、「健全なオレンジ組織」のベースが作れます。
2.オレンジ、ティール関係なく組織に一番大切なものは?
そもそもなぜティール組織にしたいのか?識者の講演や座学でテイール組織の概念を理解したとしても、自分の置かれた環境でどう振舞えばいいのかはやってみないと分かりません。実際にやってみて初めて、自分がティール組織の価値観を支持出来るのかが分かります。
「自分が描く理想の環境を実現するために、目の前の多くの問題を解決したい」といつも願っていた人がいます。その人はオレンジ組織の中でその想いを胸に秘め、「この間違った組織で辛抱して実力を付け、のちに権力を得て、最後に問題を解決してやる」と頑張っていました。
そんな想いの人が急にティール組織の環境の中に入ると「これこそ自分が求めていたもの」と思えるのか?それとも「なんだか少し違う。途中経過に過ぎなかったはずの権力が忘れられない」と感じるのか?正直に権力を求めればいいのです。それが社長自身がしたいことだからです。良いところ取りは出来ないとティール反対派が書いてましたが、マイナス要素を弱める方法はあります。
個々人の価値観(ティールの価値観に至っているか否か)は、いくら説得しても変えられません。最初ティール組織を目指していた社長も途中で「オレンジ組織の改善型」がしっくりくると分かってくるかもしれません。
形に拘らず「本当は何をしたいのか?」を考え、その目的には「どうすれば一番合理的なのか?」をティール組織/グリーン組織/オレンジ組織の要素から選び出せばいいのです。
3.オレンジ組織で改善すべき問題は?
オレンジ組織の価値観で、オレンジ組織の弊害への解決策を考えることは無駄な行為です。そもそもオレンジ組織では、社員は機械とみなし、効率や生産性のみを追求しているのですから。納期が迫れば自身は自発的にサービス残業を行い、その考えや行動が周囲に伝わります。仕事の強要等パワハラが例えなくても、社員も自発的に残業せざるを得なくなります。
職場から離れた研修室で、サーバントリーダーシップやコーチング技術を教えて、後は職場で活かして下さいと言えば人事部の担当者の仕事は済むのかもしれませんが、中間管理職の仕事は増える一方です。
つまり、オレンジ組織の常識、価値観がすべての人がオレンジ組織の弊害への解決策を考えても絶対に解決(=そこにいる人が幸せになる解決策)しないのです。最も効果的な解決策は「無駄なことをしない」ことです。社員の心が安らぎモチベーションが上がるような施策は一切やらず、「仮面を被り」ピラミッド組織のしくみが円滑になることだけを考えます。
オレンジ組織の社長の考えは「自動で動くピラミッド組織の仕組みを考える。自分は空いた時間で将来の戦略を考える」です。「今を楽しむこと」ではなく「未来を夢見る」ことです。
ティール組織の価値観、「ティールのレンズ」で眺めることが出来て初めて、「オレンジ組織の弊害」を解決することが出来ます。このことを、まず行動を起こす前に学ぶ必要があります。
4.リーダーで改善するか、しくみで改善するか
ティール組織の価値観で見て、オレンジ組織の問題は下記のとおりです。
①現場でOJTできない
②マネジメント体制がプアで機能していない
③中間管理職の負荷が重い
但し、これはティール組織の価値観で見た問題であり、理想の組織環境と比較して、解決策もすでにイメージ出来ているからです。
オレンジ組織の価値観で見ると問題点は下記のようになるのかもしれません。
①管理職は無駄なことをしている(部下へのコミュニケーション、意思確認、調整)
②必要なルールを決めていない、守っていない
上記改善施策は間違っていません。オレンジ組織は最低限、円滑に動き出すようになると思います。
但し、オレンジ組織そのものの欠点を補うことは出来ないのです。
「個々人の生産性が落ちている」「1+1が2+アルファにならない」「組織的不正が多い」「心の病気になる社員が増えた」といったコミュニケーションやモチベーションに関わる問題への解決は、それた単発のパッチ的施策では、組織に根付かず仕事の邪魔でしかないのです。
組織の形に拘らず、しかし絶対にテイール組織に価値観を持つリーダーが仕切らないと問題は解決しません。それぞれの問題へのパッチ的改善策を全体に繋ぎ直し、社員にとって自然な環境にするには時間はかかりません。ティールの価値観を持つリーダーが見て不自然と思える細かな部分をコツコツ修正していけばいいのです。その場合にティール組織をベースに行うのが最も合理的な方法です。
まとめ
まずは職場の問題点を洗い出し、枠組みはオレンジ組織のまま、問題点への改善施策をイメージしながらグリーン組織化をスタートします。平行して全社員もしくは全管理職でティール組織の勉強を開始します。
職場に応じて、ティール組織化を行う部分は全く違います。リーダーや社員の個性や能力でも変わります。時間をかけてコツコツ意見交換をして各自の考えを明確にします。それは知性や能力の高い低いに全く関係ありません。ティール組織の環境がどうしても容認できない人もいます。自分が一人で頑張り自分だけの成果で認められたい、そう願う人もいます。自分が頑張って成果を出し、その結果を社会に反映したいと願う人もいます。その違いを認識し合いましょう。
同じグリーン組織でも、部分部分でオレンジ組織ベースでいくか、ティール組織ベースか決めていきます。今はオレンジで、次の段階でティール化したいものも出てきます。前向きな試行錯誤出来ればいいのです、失敗を恐れず無駄なことをしたと絶対に責めないこと。これは非常に重要なことです。
いい加減な進め方はダメですが、細かな未来像への事業戦略的なものは無駄です。どんどん変えればいいのです。再発防止のパッチ対策を増やすことより、失敗から学ぶことを共有していきます。
スタートまでの導入方法のまとめでした。次回からもう少し具体的なコミュニケーション方法、各部署の役割等を書いていきます。

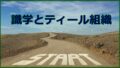

コメント