組織図も、職務記述書も、肩書もない
アンバー組織とオレンジ組織には組織図がある。組織図は複数のBOXとそれらをつなぐ線でできている。箱には肩書と職務の内容が書かれており、職務内容を見れば人々がその職務から何を期待されているのかがある程度わかる。社員は自分が就いた職務に順応しなければならない。
ティール組織ではこの前提がくつがえる。人々は事前に決められた仕事に無理に合わせる必要がなく、自分の仕事は、興味や才能、組織のニーズに基づいて自ら選んださまざまな役割と責任によって決まっていく。
方向性を定め、予算を立て、分析をし、計画を立て、段取りを整え、成果を測定し、統制し、採用し、評価し、意思疎通を図る──従来はマネジャーが担っていたこうした職務は、チーム内のそれぞれのメンバー間で分担される。
フレデリック・ラルー(著)「ティール組織」英治出版 P151 第Ⅱ部-第2章 自主経営/組織構造 より引用
引用した記述だけを読むと、通常のピラミッド組織に慣れた人は不可解に感じると思います。一体誰も仕事を指示しなくてどう仕事が回るんだろう?と疑問が湧くはずです。
通常の組織、ピラミッド組織では、(私の実体験ですが)純粋な志を持って積極的行動を取ると決まって邪魔が入りますー前例がないから予算の稟議が下りない、他のプロジェクトにリソースを取られる、部署間の力関係で上司から今回は大人しくするように言われる、揚げ句は酒の席でお前は生意気だと言われたり。
あなたに信頼できる仲間が周りに10人いると想像してください。予算もリソースも上司も、足を引っ張る環境は一切ないと仮定してください。
その10人がチームとなって突然新しい仕事を担当することになりました。かなり広範囲の業務なため、10人が分担してそれぞれの分野を責任を持って担当し、必要な場合は互いに協力し合います。予算もリソースも必要性が周囲に認められれば適切に準備できます。分からないことがあれば、社内イントラで適切な人にコンタクトして教えてもらえます。
そんな環境を想像すると、やる気が出ないわけがない。自分が正しいと思う一番効果的な方法で仕事を進めていいのです。同僚と競いあって不必要な火消し行為をしなくても、情報を独り占めして、人を動かす手段にするような浅ましい行為をしなくてもいいのです。
そんな環境なら、組織図も、職務記述書も、肩書も必要ないでしょう。自分が責任を持って仕事を担当すると宣言すれば、最初から最後まですべてのプロセスを自分が見るからです。それは必要に応じて変化しており肩書で表せないものです。
マトリックス型の組織と似ていますが、マトリックス組織のプロジェクトリーダーがプロジェクト全体のマネジメントを担当するピラミッドの頂点に位置するのに対し、ティール組織はフラットな立場ですべての作業をチームで分担して行います。時間をかけて進捗報告書を書いて上司や経営陣に説明することもないので、周囲に自分達の役割を示す必要もないのです。
当然、そのようなチームワークを築くにはそれなりのトレーニングが必要です。個人のスキルアップだけでなく、チームとしてのコミュニケーションの取り方、ミーティングの仕方も試行錯誤を繰り返し、自分達の環境に合ったものを模索する必要があります。
そして、一般の会社≒オレンジ組織では現在ギリギリ許されているような他人に対するハラストメントも許されません。そのような行為を行った場合は会社を去るという誓約書にあらかじめサインしてもらっているティール組織があります。
社長がそのような環境を真に望み、片腕社員に導入過程を任せっぱなしにせず自ら失敗を恐れずに模索していけば必ず望む環境は築くことができます。
「円滑なコミュニケーション」は、そもそもティール組織だけで必要な環境ではなく、オレンジ組織でも実践すれば居心地が良くなり心理的安全性は格段に上がります。ティール組織はこの土台(=社員の心理的安全性)を築いた上でないと機能しないからしっかり向き合っているのです。
役職は地位を表す一種の通貨
役職は地位を表す一種の通貨だ。あらゆる通貨がそうであるように、役職もインフレの法則に従う。多くの企業では、役職の種類がどんどん増えているように見える。ヴァイス・プレジデント、シニア・ヴァイス・プレジデント、ジュニア・ディレクター、シニア・ディレクター、そして最高責任者ですら種類が増えている。オレンジ組織の世界観では、人々が一生懸命働くのは、昇進して大きな肩書を得るためというのが共通認識だ。
オレンジ組織の視点からすると、役職はエゴにとっての蜜のようなものだ。あまりにおいしくて夢中になるのだが、結局は健康を害してしまう。役職に社会的名声が伴っていると離れられなくなる。そしてたいてい自分がその役職「そのもの」であると勘違いしてしまう。階層制度の中に入ると、自分はだれかよりも「上」だ、「下」だと考え始める。ほとんどのティール組織には、ある意味当然だが役職がない。
フレデリック・ラルー(著)「ティール組織」英治出版 P153 第Ⅱ部-第2章 自主経営/組織構造 より引用
役職がないと言うと、全員が同じ仕事をしていると誤解されがちですが、実際は様々な仕事を担当していて、中には従来のCEOと同じだけの広い範囲の仕事をしている人もいるようです。
多くのティール組織では社内イントラネットの様々なtoolで、誰が今どんな仕事をしているかが分かるようになっている。そして過去の役割も記録されているため、他の社員から質問したりアドバイスをもらったりできるようになっている。
オレンジ組織の場合、役職に責任が付いてくる。責任が明確という点は一見良いことのように思えるが、実際はうまく行っているときは放置であり、問題が発生し顧客から叱られたときなどに大騒ぎして部下に責任を負わせ(首を切ったり左遷させたり)、根本的解決をせずパッチ的迅速な対応を中間管理職に強いて社員のやる気を削ぐだけになりがちです。
ティール組織の場合は、そのような役職の責任者がいない代わりに一担当者がすべての責任を仲間に公約していることになります。たった1人の管理職への説明責任ではないのです。仲間全員が管理職になるのです。
まとめ
組織に階級を作ると、どうしてもピラミッドの上に行くほど強力な権力を持った人が出てきます。その人が有能で人格者であったとしても、個人のパフォーマンスと短期利益を重視するオレンジ組織ではやる気を削がれる社員が多数でてきます。
その権力の弊害を防ぐために、階級をフラットにし肩書さえも無くしてしまおうというのがティール組織の考え方です。倫理観からではなく、そのコミュニケーションスタイルが最も合理的で、もっとも利益が出る方法だからです。
いきなり、完全なティール組織を作るのはなく、ティール組織が最も進んだ組織、最も合理的なコミュニケーションが行える組織である理由を社員全員が理解し、オレンジ組織のままで、そのエッセンスを取り入れていけば、社員にとって住みよく、(オレンジ組織の視点でいえば)利益を出せる組織環境が作れます。
まずは、全社員にティール組織の概念を説明し、どれだけの社員がティール組織の概念を理解し、心の底から共感できるのかを確かめてみることです。
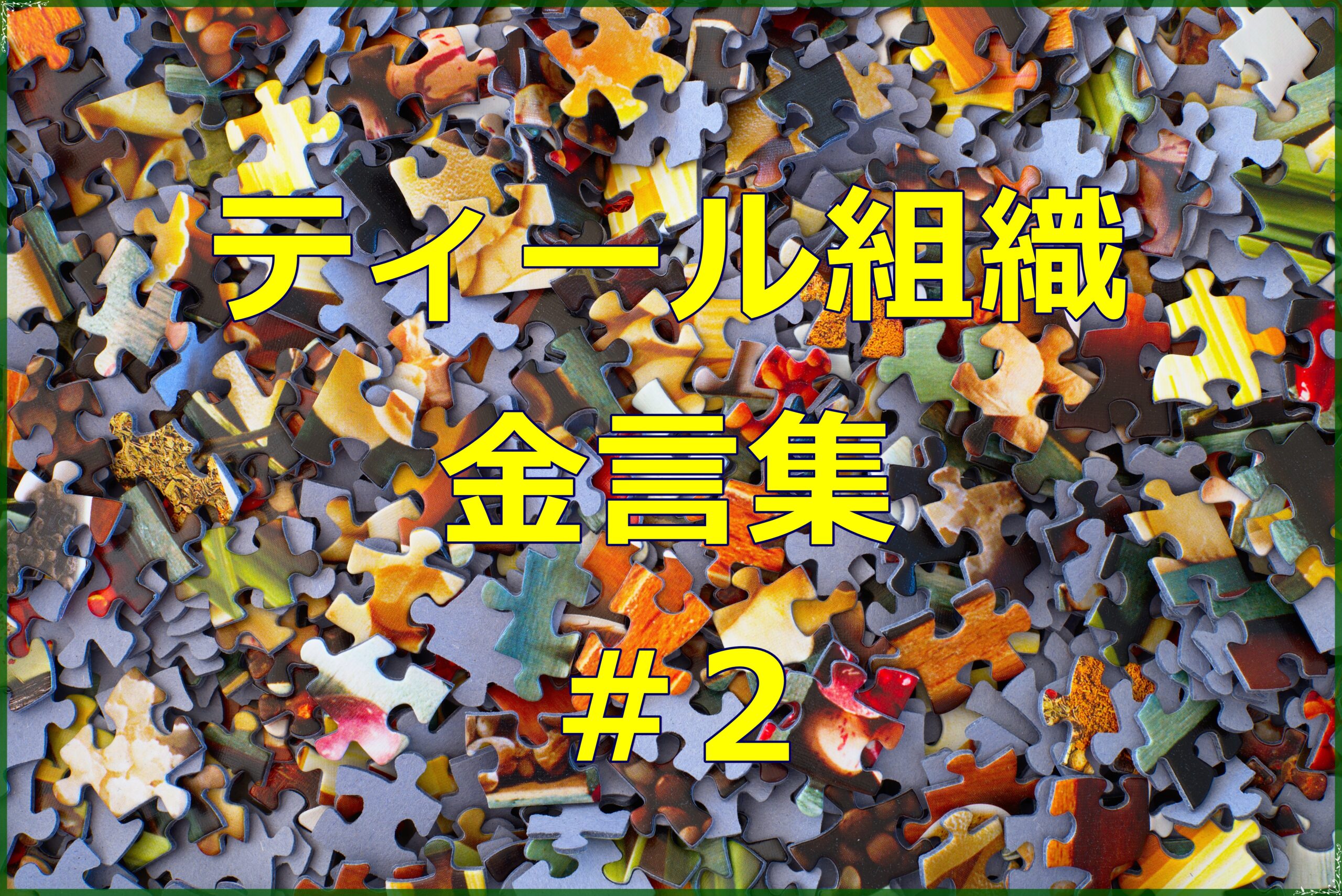

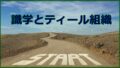
コメント