1.変革のリーダーはとにかくブレないこと
組織を変革しようとする場合、必ず誰かが反対します。確かに誰かにとってはデメリットしかない場合があり、反対したくなるのは理解できますが、多くは感情的なものであるため、全員の合意を取り付けるのは難しく、最後はリーダー(=社長)の強権発動で動かすしかないようです。
現場は大きく混乱し、暫定的措置や個人的に無理を続けて乗り切ることになるため、一旦決めて動き出したら矛盾のないよう、ブレないように走り続けるしかありません。
決して間違いを起こさないように、ではなく、常に情報共有や意見交換を行い、試行錯誤を前提に細かな点も修正していくことが大切です。
特に、従来のピラミッド型の組織からフラットな組織に変更する場合、必ずそれまで仕切っていたミドル/シニア・マネジメント層の反対があります。
状況を説明しても最後まで納得しないマネジャーは、「他人に厳しく自分に甘い人」が多いように思います。そういう人に限って、現在進行中の業務のキーになる部分を独り占めしていたりします。
その要注意人物の扱いを任されたマネジャーは貧乏くじを引かされた気分になります。
この問題は組織がどれだけ病んでいるかで違いますが、どこでも起こる可能性があります。
社長の立場からすると、些細なことなので部下に任せたいところですが、要注意人物は保身のため懇意にしている顧客や上司に取り入り巧妙に抵抗する場合もあり厄介な問題です。出来るだけ状況を把握し、最初に示した方向からどんなことがあっても最後までブレないようにしてください。
もし途中で方針を変えると、粛清を任されたマネジャーが梯子を外され、悪者になったり、居場所がなくなることになります。
過去の実例を挙げます。
繁忙期の業界における成果主義の組織で、疲弊した社員が多い状況での組織変更でした。
2.周囲に厳しい職人気質
ある技術部門で50人ほどのエンジニアをまとめているシニアエンジニア(以下=Aさん)がいました。職人気質なのか現場の仕事をしたいと言い、課長昇進を断っていました。
この部署に問題があり改善してほしいと私に依頼が来ました。「関連部署からの協力依頼を渋り、いろいろ難癖をつける。」「彼だけが前面に目立ち、他のメンバーが出てこない。」「もっと人材を育て効率を上げて欲しい。」とのことでした。
現状を調べてみると、確かに周辺部署からの業務依頼を断っていましたが、やみくもに断るのではなく、部下を過負荷から守るためでした。
そして他のメンバーの育成については、週1回進捗会議を開き、全メンバーの業務内容をレビューして、非常に厳しく指摘していました。
熱意を持って指導しているようですが、厳しい指導にメンバーは委縮し、伸びているのはタフで優秀な一部メンバーだけでした。
つまり非常にストイックな性格で完璧な仕事を目指し、それを周囲にも押し付け、結果的に一人空回りしている状態でした。
また、「他人に厳しく自分に甘い」ところがあり、ほぼ毎日終電近くまで仕事をして翌日は11時すぎに出社するので、フレックス制でない周囲の派遣社員は残業時間が増えていました。
Aさんに組織変更についての話し合いを求めましたが、「勝手にやっていいから。但し今まで自分が築き上げたレベルを維持してください。」と言い、協力してくれませんでした。
調査した状況を役員に報告し、役割を分けた4つのサブグループに分けることを提案しました。そして、それぞれをメンバーから選出した新しいサブリーダーに任せました。
Aさんも一つのサブグループのリーダーとして残しましたが、不満げでやる気を無くしていました。新しいサブリーダーへの引継ぎも完全ではなく、混乱を招き一時期業務効率が大きく落ちました。やがて、Aさんに対する、新しいサブリーダー達の対応が徐々にぞんざいになってきました。新しい役割に自信をつけ、今まで抑えてきた感情が出てきたようで、Aさんが孤立してきました。
新しい組織が機能し出した頃、Aさんに異動の打診があり、本人は拒否したようです。
その後、Aさんへの更生措置は尻すぼみとなり、いつの間にか立ち消えとなりました。
権限が分散されたおかげで、以前のような極端な不満が周囲から出なくなり、引受先もないことから保留のままで終わりました。
3.これで良かったのか?
結果的に組織全体としては改善されたので良かったのですが、Aさんへの指導という点では不十分でした。
しかし、そもそも何が正しいかの価値観が不明確な状況では、一概にAさんばかりを責めるのは酷で、誰かを魔女裁判のようにつるし上げにしてしまいかねない危うい場面だったと思います。
このような部分的な改善としては、Aさんをとことん追い詰めなかったことも含めて、成功と思います。
4.もっとうまくやるには「情報開示」を
中間管理職は、良かれと思って自分に課せられた業務をこなそうと必死に頑張ります。
そして、何とか80点取れるまで頑張り、それが限界だったときは、100点を目指し周囲を巻き込んでしまいます。Aさんはそうして自分にも周囲にも無理を強いてきました。
それは決して本人のせいでもないですが、組織変革とは全く別の問題であり、今まで隠されていた膿が組織変革で噴出したようなものです。組織を大きく変革しようとすると、この問題がいたるところで起こります。
では、どうすれば救われるのか?
それは情報を全社員に開示することです。
社長の意思として、全体でどう変革したいか?どんな価値観を持ちたいか?を示し、社員自らの意思で、会社に貢献できる役割を選ばせることです。
社長がリーダーの場合でも、管理職全員の立場を思いやることが出来ない規模の場合は、どうしても別の者に実務リーダーを任せる場合があります。
実務リーダーも間違った理解、判断をすることがあります。社員が実務リーダーの言動に社長とのずれを感じたら、「それは違うと思う」と言えるようにするためです。(そもそも自由に意見を言えるような雰囲気にすることも重要ですが)
5.人事に丸投げはしないこと
人事だけに任せるのはやめましょう。
自分より立場が下の人の気持ちを察することが出来ない現場マネジャーより基本的な部分でマシな人が多いようですが、根本的な部分で勘違いしている人が多く、人事が言う常套句「あなたに任せる仕事はありません」的発言を平気で言いがちです。
ダイアログやコーチングを勉強した現場マネジャーに任せるべきです。
6.グレーなマネジャーの取り扱い
今回の例でも、Aさんは非常に優秀なエンジニアだということなので会社に貢献してきたと思うし、これからも貢献してくと予想できます。
ただ、周囲へ与えた悪影響をどう判断するかは難しいところです。彼が職場の雰囲気を重く暗いものにしたことは確かで、そのことが原因で職場を去った派遣社員もいたと聞いています。
すべての社員にとって居心地の良い環境とは、倫理観があり職場の空気が濁っていないことだと思います。
理想的には、ティール組織で記述されているように、ダイアログの手法を使って価値観のすり合わせをし、価値観の合わない社員は自然に入れ替わっていくようにするべきです。ただ、組織変革の最初の段階でいきなりそこまでレベルを上げられないので、どうしても平行で作業を進め、何回も段階を経て改革を進めていくことになります。
その過程において、「仕事は出来るが問題児」に短期的に頼らざるを得ないことがあり、非常に嫌な思いをします。
でも諦めてはいけません。そういった相手に策を巡らされ、悔しい思いをすることもあるかもしれませんが、決してあきらめず、コツコツと理想に向かって活動を継続すれば、ある時期を過ぎると改革は加速してきます。
潮目が変わって彼らを排除出来るようになったとしても、あくまで紳士的に接して、彼らのレベルまで落ちることのないように。
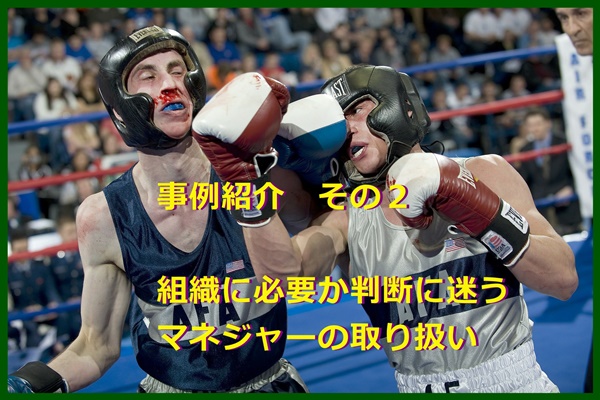

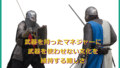
コメント