通常の組織(アンバーやオレンジパラダイム)をティール組織に変容させようとすると、どうしても過渡期には生産性が落ちてしまいます。それを防ぐためにリーダー(社長)達で工夫しながら進めてしまうと今後は社員がやる気を無くしてしまいます。
そのさじ加減を考えて、社員から信頼されつつ「ティール化過渡期の人材スクリーニング」を行う方法を考えてみます。
目指すのは「人が活きる集団」であって「チームワーク」ではない
日本人は昔からチームワークが良いと言われています。しかし、それは自己を犠牲にして上からの命令に従うスタイルがあってのことです。犠牲とは、何かに辛抱している精神状態です。それは個人の自由な活動の妨げになります。自ら湧き出るアイデアを抑え、辛抱する必要はないのです。
優秀な指揮官の下で動く軍隊が平地で戦う場合は適しているかもしれませんが、夜間に未知の相手と戦うゲリラ戦には弱い部分があります。個々の臨機応変な動きが弱いのです。
このVUCAの時代において、「自分で考えて動ける優秀な個人の集団」を作ることは最重要課題です。
ティール組織導入時初期のスクリーニング作業
この作業はティール化の予定がなくても、社員の意識を改善するには有効な作業です。参考にしてください。
行うプロセスは下記の3step。実際には過渡期に発生する様々な問題、例えば「現在進行中の効率を落とさない」、「一部社員だけで勝手に進めて、その他社員のやる気を削がない」、「社員にやる気があっても質が低すぎて意気消沈することを防ぐ」などを回避しながら進めないといけないので、経験やノウハウが必要になり、進め方は臨機応変に変えることになるので、あくまで標準的な手順です。
Step1:恐れを取り除く;オレンジ組織では当たり前でも、実は潜在意識で恐れを抱く環境を改善
Step2:ルールを定め、腐ったリンゴを排除する;従えなければ排除せざるを得ない環境を作る
Step3:質を上げていく;環境を整え、後は自ら努力して質を上げていく
Step1: 恐れを取り除く
現場を厳しく楽しいOJT環境に変えるのに、権威主義で優等生タイプの管理職は百害あって一利なし。ティール組織を導入する気がなくても、オレンジ組織においても、管理職は自覚なしに害をなす者が多く、大幅に人数を減らすか管理義務を減らすべきです。
例えば、部長ひとりだけ残して課長係長クラスは全員一般社員に戻ります。実務業務指導役、コーチ役は別途アサインする、とかです。社員の「恐れ」に関わるマイナスの要素をコツコツ1つずつ解決していきます。これがすべてにおいて最初のステップです。
「評価制度に情意評価を追加する」、「1人の上司からの評価を廃止、もっと時間をかけ精度を上げる策を考える」、「年功序列や家族手当等、いるだけでもらえる手当は廃止。代わりに成果報酬を上げる」挙げればもっともっとアイデアは出るはずです。
要は、「前向きに頑張れば報いられる」と社員が思うにはどうすればいいか?を真剣に考えればいいだけです。
Step2: ルールを定め「腐ったリンゴ」を排除する
仕事は出来るが人間的に問題がある社員を排除します。普通の会社(オレンジ組織)では成果さえ上げれば許されていた振舞いを厳しく罰します。自由と責任は両輪です。「あの人は仕事が出来るから何をしても許される」と社員が思うような環境では人は育ちません。「俺も昇進して同じような振る舞いをしたい」と考えるような若者が育ちます。私は実際にそんな光景を見てきました。
「自分の意見をはっきり言う。そして自分の発言にも仕事にも責任を持つ」。そんな人材を育成したいのなら、毅然とした態度で現場の膿は排除しましょう。
Step3: 環境を整え、社員の質を上げていく
上記Step1,2の改善が進まないと、社員は自ら変わろうとしません。自ら考え努力しようとしません。これで社員は自ら動ける状態になりました。
さらに環境で準備しておくのは「情報共有」です。この時点ではトップが考えている、改革プロジェクト構想や関連情報は全社員と共有されているべきです。
「オレンジ組織の発展型」、「まずは社員ワンマンでティール化を目指す」、「いきなりティール組織を目指す」のどの戦略にするかで情報開示は変わるかもしれませんが、基本はすべての情報を開示するべきです。
ティールでもオレンジでも、組織環境を改善していくと、個人が嫌な思いをすることが減ります。
変な社員は自然淘汰され去っていきます。そこで初めて組織のOJT機能が効果を発揮するのです。
目指す環境
気の合う仲間の集団を目指していません。仲良くすることを優先すると、「滅私奉公(私心を捨てて、公に尽くすこと)」のニュアンスが強くなってしまいます。互いの尊厳は守りながら、自分の意見は冷静に遠慮なく主張できること。日本人には苦手な分野です。しかし、これを克服しないと次のステップには行けません。
日本人は自分主張する機会も少なく、無難に集団生活を送れることを良しとしてきました。最近どんな状況でも自分の意見をはっきり言える人が若い世代に増えています。その人達が組織の中でうまくコミュニケーションでき、居心地が良いと感じる組織環境を作ることを目指します。
具体的な進め方
基本はいかなるときも、「社員の可能性を信じること」です。大体下記のように進めていくのが無理のない方法です。
スタート前の環境
まずリーダーである社長がティールパラダイムを理解され、それが一番自然な環境と信じられていること。
以前から世の中の常識(オレンジパラダイムの世界)に違和感を感じていて、もっと自然な、もっと感情や理にかなった方法はないか? と模索されていて「ティール組織」を知った。いろいろ下調べをして改善プロジェクトをスタートさせる決心をし、役員達の了解も得た。そんな感じです。
活動開始
最初の一歩が難しい。一番大切なのは、やはりリーダー(社長)がぶれないこと。成功を信じ切ること。少しでも不安な気持ちがあると「恐れ」となり、社員の可能性を信じず早めに予防策を取ってしまう。それを社員は敏感に感じ取り「やはり信じてくれていない」と思い冷めてしまいます。
スタートアップの組織の場合は、社員の可能性を信じ、すべての情報を開示し、一緒に活動を開始することが比較的容易です。
現在進行中の業務があり、生産性を落とせない場合は、社員の潜在能力を冷静に見積もり、下記の選択肢からベストの方法を選びます。
その1:社長がリーダーとなり、ワンマン体制で活動開始。ゴールまでの計画などの情報は開示し、まずは社員のやる気を上げることに専念する。
その2:最初から全員にすべてを話し、全員参加の会議(とことん話せるホールシステムアプローチ)で相談しながら計画を一緒に作っていく。
その3:1と2の折衷案、全体は社長ワンマンでスタートし、一部の事業だけでサンプル的に自主経営を始める。その経験を元に全社展開する。
平行して、社員全員がティール組織に関する基礎知識を学習する。そして、職場の相互コミュニケーションに関するルール作りを開始する。
管理職を廃止する。また、コーチを担当する者を募り、学習を経て業務開始する。
自己組織化が目的ではない
自己組織化(=秩序や構造が自然にできあがる不思議な現象、リーダーがいない組織のこと)にすることが目的ではなく、「より良いサービスの提供」や「より有意義な仕事」を実現することが目的です。
スタート時に社員のスキル不足や意識を高める必要があるのなら、優秀なリーダーに牽引してもらうのも間違いではありません。
自立心が育ちにくいマイナス要素も考慮した上で、 可能な限り「現場のチームメンバーが中心となる」工夫をすることで、効果が期待できる組織運営が可能です。
どの組織にもあてはまる変革メソッドなど存在しない。組織ごとに異なり、つねに現状に合わせて自分達で工夫しながら作り出していくことが大切です。
質を高める
職場のバリューチェーンによって、個人で活動するかチームを組んで活動するかを決めます。チームを組んで活動する場合、リーダーは設けず全員平等です。
但し、各自が自分の得意な分野を生かし、協力し合う中で自然と尊敬され、一目置かれる扱いを受ける人が出てきます。また、逆にチームに迷惑な行為をする人はメンバーから注意され、それでも改まらなければ紛争解決のための次のステップに行き、最終的には会社を去ることになります。
もっとも、チームを組むこと自体が自由意志なので、紛争になる前に迷惑な人がいるチームから自然と人が離れていくことになります。現場で仕事をしながら不便に感じたことをどんどんフィードバックして組織環境は改善されていきます。
求められる個人の能力

組織は自分を守ってくれていると安心すると、人はどんどん自由な発想が出来るようになります。そして、このような環境で一番伸びてくるのは、「自己効力感(セルフ・エフィカシー)」です。
自己効力感とは、「できると自分を信じられる力」です。自己を尊重し、自身の価値を感じ、自身の存在を肯定できます。
この力が不足していると、自分に自信がなくなり、他人と比較したり攻撃したりして自身の存在理由を確かめようとするのです。コーチはこの能力を高めるために社員1人1人と会話し、能力を引き出していきます。
落とし穴に気をつける
他人の代わりに考えてしまう
組織が力を発揮するためには、全社員が連携しあい、それぞれの役割の中で、各自が出来る限りの役割を果たしていると思っているはずです。
ところが、何がベストかを他人から決めつけられると、本人のプロ意識が無視された気持ちになります。より良いものをつくり出す意見や提案は歓迎されるべきですが、相手を気遣うコミュニケーションが重要になります。心無い会話は、容易にメンバー間の遺恨となり、連携を阻害することになります。
どこまで他人の仕事に口を挟まずにいるべきか?どこから言うべきか?本人の学習や経験を積む機会を奪うことがどこまで許されるのか、話し合う必要があります。
チーム内に階層を生んでしまう
チームメンバーで連携して作業をするうちに、誰か一人がその分野での「ボス」役を演じることがあります。そうすると平等性が失われ、自主経営チームの活力が弱まってしまいます。
どう防ぐかをメンバーは話し合う必要があります。ティール組織のパイオニア企業では、持ち回り制にしてあまり長期間同じ仕事に就かないようにしているようです。
管理しすぎてしまう
オレンジパラダイムに慣れた人たちは管理するルールづくりに慣れすぎているので、ついルールづくりを際限なく続けてしまいます。
チームメンバーが自分で判断する余地を奪うことにならないよう、最低限のルール(フレームワーク)に留めておきます。
現場の環境整備が重要
チームが現場の責務を果たすための仕組みが必要です。チームに裁量の余地を十分に与え、価値ある情報を提供するといった環境整備がなければ、チームメンバーは成果を出すことができません。
間接部門に依頼するのではなく、各チームで積極的に作っていく必要があります。

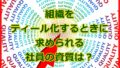

コメント