組織改革で成果を出すために必要なたった3つのスキル
組織改革に適した人材は必ずしも、仕事ができる人材ではありません。
仕事ができる能力である「問題解決能力」が優れている人は、逆に組織改革の活動の妨げになる場合があります。
目の前の問題を1人で早く解決することが求められているわけではないからです。
組織改革はテーマが大きく深く、1人の手に負えるものではありません。また活動開始時の目標設定が難しく、進みながらゴールの詳細化を行うため、今まで個人的リーダーシップでプロジェクトを牽引してきた人では難しいかもしれません。
様々な考えを持つ社員をまとめながら経営トップの意思に沿った方向に導く力、現場の社員1人ひとりの気持ちを察し、便宜を図っていく調整能力、他人を思いやる気持ちが要求されます。
そんな素養のある人材がいれば、改革は成功したも同然です。
後は下記に示すたった3つのスキルを習得すれば良いのです。
その1:「会社は(自分は)どうありたいのか?」が明確であること
個人でも組織でも同じで、「どうありたいか?」を明確にする必要があります。「どうありたいか?」は「やりたいこと」とは違います。「やりたいこと」、「なりたい状態」は目標であって、あり方は物事のあるべき姿、価値観です。
「自社(自分)はこういう存在でありたい」という存在理由です。これが明確でないと、社員が本音で話し合いなどできないし、各自がどう感じるか?を共有できません。少し気持ちを落ち着かせて、自分の心に聞けばいいだけです。日々様々な感情や事情が渦巻く環境で過ごすために、感情を殺す癖がついている自分に自問してください。
その2:「(知識を)習う」のではなく「学び方を学ぶ」 ことができる
どんなことでも同じことが言えるのですが、知識やノウハウだけあっても実践では全く通用しません。自分で何度も失敗し試行錯誤しながら自分のスタイルを完成させていくか、師匠から学んだことをとことん体に覚え込ませた後、独自の方法を編み出す(守破離)か、です。どちらの方法でも成果を早く出すコツは共通していて、完璧を求めず60%の完成度でもいいので、どんどん先に進むことです。どんどん学んだことを実践して、人に教え、新しいことを体に覚え込ませる。進みながら何度でも細かな修正を繰り返せばいいのです。
この新しい情報の取り込み方法が身に着くと、本を読んだり、研修を受けたりして得た情報から、必要なものを抽出するスピードが速くなります。
その3:一旦決めたら迷わずやり抜くことができる (IQ、才能でない)
新しいことを始めると、成果が表に出ずに、見えない部分でノウハウを積み重ねる時期があります。ある時期を過ぎると急激に成果が出てきます(=成長曲線といいます)。
やみくもに進むわけではありませんが、マイルストンまで進み、細切れに軌道修正する進め方が必要になります。
今まで自分の部署だけをしっかり守ってきた完璧主義の管理職の方々は不安がり、最後は「以前の方が良かった。むちゃくちゃにされた。」と怒ってくるでしょう。
この人達を黙らせるのは本当に難しく、厄介なものです。改革の業務を任そうにも柔軟な思考力に欠けている人もいますが、排除したらもっと厄介なことになります。
何度も最終ゴールやマイルストンを説明して、追い付いてきてもらうしかありません。
普段から考え続けていることは、必ず現実になります。何度も何度も計画を見直し、想像し、詳細化します。
そのしつこさがプロジェクトを成功させる秘訣です。

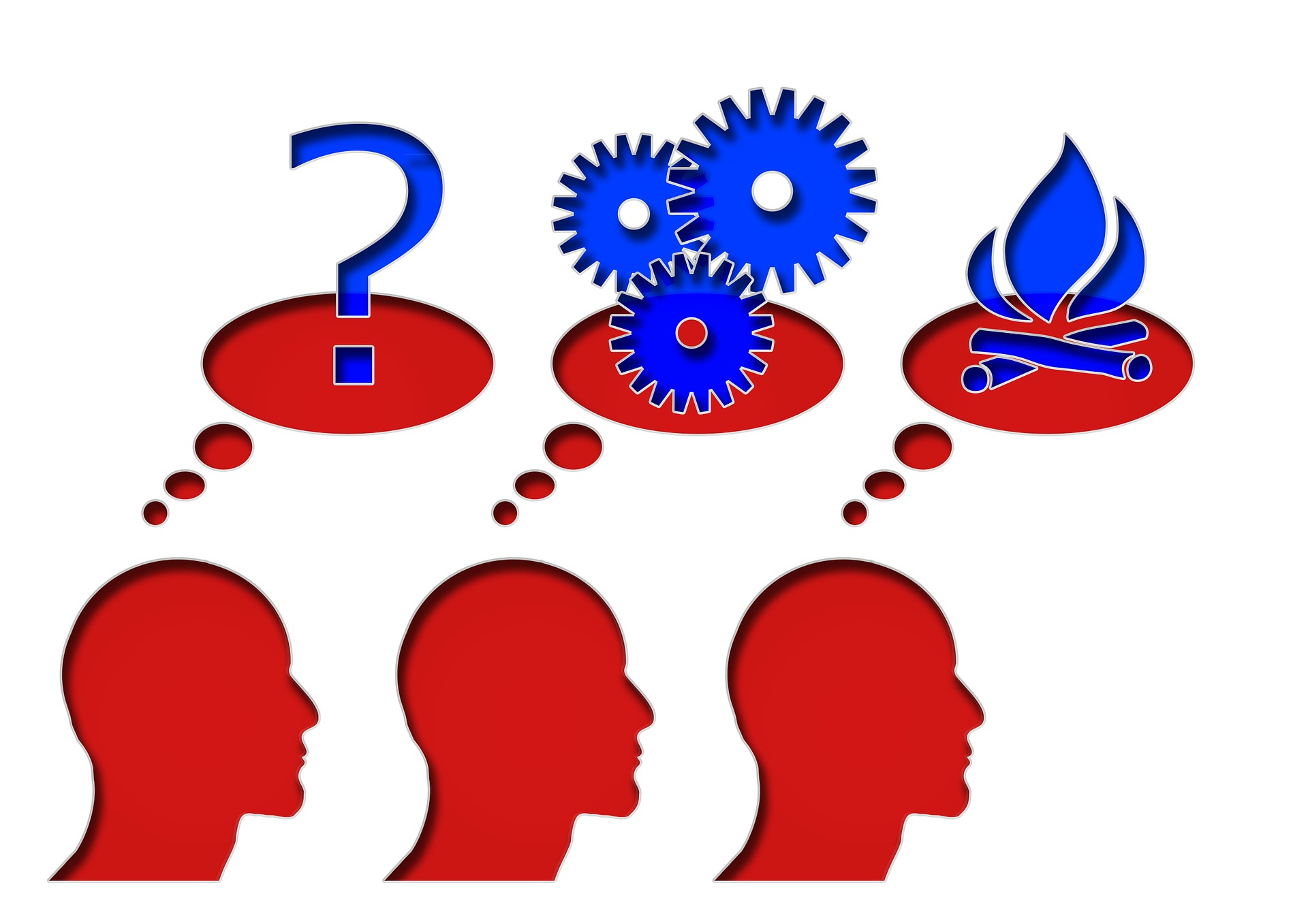

コメント