組織と世界の二極化
これからは、上司が管理するピラミッド型組織が廃れてきて、「一人ひとりが契約で繋がっている責任ある大人の集団」と「全体性と存在目的の慣行により一枚岩となった、各自が柔軟に対応できる、熱量のある集団」の2タイプが増えてきます。
前者は中途社員中心の組織、後者は新卒も参加可能な人材育成機関を兼ねた組織です。Web3.0とAI化は、意図せずに「倫理的に間違っているが世の中に蔓延している不正」を正すことになります。
情報の可視化と公平性が基本となることから、倫理観でなく合理性の観点からコミュニケーションが改善されるのです。
ピラミッド組織のトップで情報を独占し、部下に指示をする古い価値観の人達は世代交代により、減少していきます。
もう少し先になるのかもしれませんが、全く新しい価値観のセレブリティ(大谷翔平のような富と権力に執着しない人々)が予想以上に急速に世界を変えていきます。
ITの進歩は宗教やスピリチュアルも合理的に取り込み融合していきます。占い師やカウンセラーも淘汰され、本物しか残れないでしょう。
倫理観からでなく、心理学も含めた合理的な解決策としてAIが推奨する解決策はどんどん人間的になるのです。AIに「仕事を取られる」のではなく、「人間にしかできない仕事に専念できる」と捉える。
恐れから来る所有欲を卒業した世代だけになったとき、移動エネルギーの消費さえも減るようになります。科学の進歩により実際に移動する必要性が減ることから、行動範囲が狭まり、かつ人口密度は全域に拡散するからです。
かつてピラミッド組織が機能していた理由
昔は機能したピラミッド組織ピラミッド組織がうまく機能していたのは‘90年代です。
なぜうまく機能したのか?
①年代別人口分布が理想的で年代に応じたポストが準備できた。
②終身雇用、社会保険で将来を保証されていた。
③世の中の変化が穏やかで予測がついた。
④正規雇用社員が多かった。(‘90年に2割、今は4割)
今の組織環境は最悪の状態かも知れません。
コスト削減が進むなかで、コミュニケーション改善や現場のメンタルケアをしていた課長クラスの「一見あまり仕事が出来ないがいてくれると癒されるいい人」的人材が淘汰されました。
部長クラスの管理職は、仕事の仮面を被ったサイコパス的な人しか務まらなくなりました。廃れ行く、今の組織で出来ることは?
多くのピラミッド組織(=階層組織≒オレンジ組織)では上司が仕切っているので、社員自ら改善できることはほとんどありません。悲しいことですが、仮面を被りストレスから自分を守らないといけません。
この最悪の環境で、現場で無難に改善できることは?
強いて挙げれば、現場で改善出来そうなことは1つだけあります。それは「進め方(=マネジメント)」と「議題(=実務の段取り)」を区別することで、現場のマネジメントを可視化するのです。
具体的には、上司や会議の進行役に従うのではなく、自分が全責任を持って仕事を仕切ることです。「議題」は仕事そのものの話題であり、「進め方」は集団の活動の進め方(=リーダーの仕事)であり、大げさに言えば権限委譲になります。
「進め方」「段取り」を考えて、仕事をする力を養い、リーダーとしての思考方法を日常で鍛えることになるので、反対する上司は少ないと思います。
ピラミッド組織では、「集団の進め方」は上司が勝手に仕切り(悪気はないのですが・・・)、「仕事そのもの」は部下の責任として急に割り振られます。これでは、部下のやる気を削ぐことになります。
このプロセスを採用すると、若手社員の「仕事の勘」が伸びてきます。その弊害?として、上司より自分の判断が合理的だと感じることが増えていきます。そのときに組織がどう対処するかで、その後の若手社員が組織に残るか否かが決まります。
根本的な改善を行うには?
若手社員の実力を上げていくと、段々とマネジメントにおいて我慢を強いる状況になってきます。本当は根底からしくみを変えないとスッキリしないのはみんな分かっていますが、それを言い出す人がいないのが現状です。こんな、職場を改善するヒントが、「なぜ弱さを見せあえる組織が強いのか(英治出版)」にありました。
外部研修や1 on 1とかのコーチング指導の効果は、それほど期待できないというのです。
幹部向けのエグゼクティブ・コーチング、有望人材の育成プログラム、メンタリング、企業内大学、職場を離れて実施するオフサイト研修や合宿研修、リーダーシップ開発などは、それぞれ異なる取り組みに見えるかもしれないが、ある共通する有害な特徴をもっている。
その点で、これらの施策はすべて、「能力開発に関する20世紀的なアプローチ」と位置づけられる。
その有害な共通点とはなにか?
第1は、継続的ではなく、ときおり期間限定で提供されること。
これでは頻度も強度も不十分だ。人を真に成長させることの難しさを考えれば、あまりに弱々しいはたらきかけと言わざるをえない。
第2は、「特別」なものであることだ。
日常の仕事とは切り離された活動になっているのだ。そのため、学習成果の移転とコストの両面で難しい問題が生じる。仕事と離れた場で強力な学習が後押しされたとしても、そこで学んだことを、以前と変わらない職場で実践するのは至難の業だ。それに、研修そのものにかかる費用と、研修中に社員が業務を離れることのコストを両方負担し続けるのも容易でない。
第3は、対象がメンバーのごく一部に限られること。
たいてい、5~10%程度の「高い潜在能力の持ち主」とみなされた社員しか参加しない(ほかの90~95%の人の能力を否定するに等しい)。
第4は、これが最も重大な問題なのだが、開発の対象が組織ではなく個人に限られる点だ。
20世紀型の人材育成法では、組織がメンバーの能力を大きく高めたければ、組織外の新しい要素を「付け足し」て与えるべきだと考えられている。コーチやメンターを雇ったり、研修プログラムや講習会を実施したりする。これでは、組織自体はまったく変わらない。言ってみれば、ガソリンの性能は強化されても、エンジン自体は同じままなのだ。
ロバート・キーガン/リサ・ラスコウ・レイヒー著 英治出版
「なぜ弱さを見せあえる組織が強いのか」P19より
つまり、研修室の座学はやめて、現場で日々実践しながら学ぶことが一番なのです。
現場を効果的な能力開発の場にする方法は、少人数のチームを作り、そのチームに仕事の全責任を委譲することです。そして、放任ではなく、求められれば助言をし、適切なサポートをします。
彼らは日々の仕事のなかで悩み、失敗をしながら成長していきます。
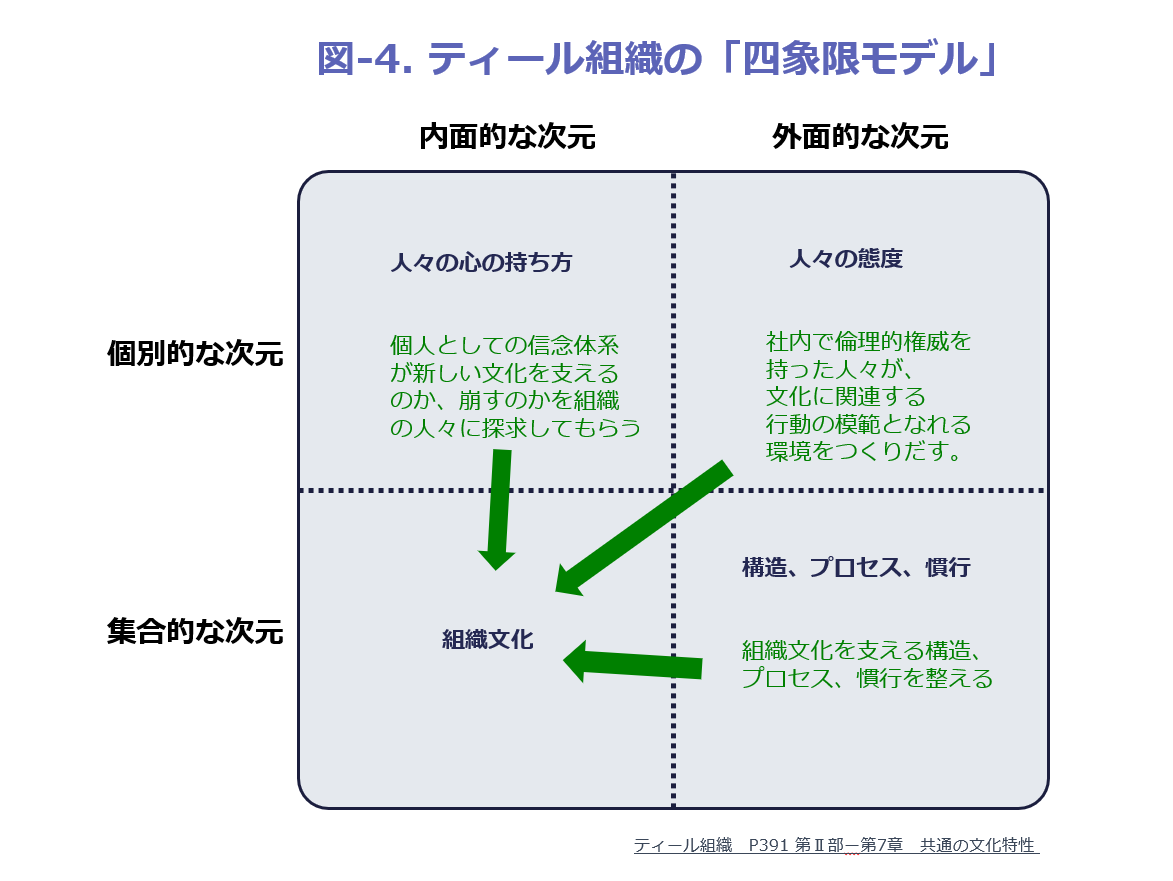


コメント