たびたび成功事例に挙げさせて頂いた(株)日本レーザー会長 近藤宣之氏の著書「ありえないレベルで人を大切にしたら23年連続黒字になった仕組み」(ダイヤモンド社 2017年3月出版) を紹介させていただきます。他に下記の3冊も読んだのですが、それぞれに特色があり、どれもお勧めです。
・「社員を大切にするから黒字になる。甘いから赤字になる」 あさ出版 2018年9月
・「社員に任せるから会社は進化する」 PHP研究所 2018年12月
・「倒産寸前から25の修羅場を乗り切った社長の全ノウハウ」 ダイヤモンド社 2019年4月
「ありえない~」と「社員を大切にする~」は近藤会長がティール組織を知る前に書かれた書籍ですが、ティール組織の考えと重なる記述が非常に多く驚きです。比較的初期に著された「ありえない~」は近藤会長のお考えや日本レーザーの独特の仕組みについてバランス良く説明されています。
その次に書かれた「社員を大切にする~」は質問が多かったしくみの詳細な部分について、実務資料を載せて解説されています。
「社員に任せる~」は当時話題になり始めたティール組織を意識しながら、日本レーザーの仕組みを比較分析されています。最後の「倒産寸前~」は社長目線で数々の難関を切り抜けられたかを記述されています。
日本レーザーとは?
レーザー専門商社の草分け。日本で最古、最大のレーザー及び光関連製品の専門企業。日本電子株式会社の子会社。2007年に独立、55人の社員全員が株主。(パート、派遣、嘱託社員も株主)。
独立後、親会社がなくなったので、ピラミッド型の縦割り組織から、横割りのフラットな組織に変わった。「お金」や「市場」にフォーカスした経営ではなく、「人」にフォーカスしながら利益を上げる経営に変わった。「社員=株主」なので、社員の中に業績に対する自覚、責任、当事者意識が芽生えた。
http://www.cowtv.jp/channel/boss/550kondou/01.php
「ありえないレベルで人を大切にしたら23年連続黒字になった仕組み」とは
著書「ありえない~」では、29項目に分けてしくみを説明されていますが、あまりこの項目に拘らず、印象に残った部分を書いていきます。
企業の発達段階に応じてリーダーシップやマネジメントは変えるべき
順番が前後しますが、巻末に特別付録として問答集があり、そのなかで、「トップダウン型とボトムアップ型リーダーシップ、どちらが望ましいか?」との問いに、「企業の発達段階に応じてリーダーシップやマネジメントは変えるべき」と答えておられます。
Step1:再建期はトップダウン型で経営刷新
Step2:モチベーションを上げる期間
Step3:社員の当事者意識を高める(2007年のMEBOなど)
Step4:社員が会社から大切にされている実感を持てる経営へと深化
最後に:「自己効力感(注)が高い社員による」自己組織化の展開へ変貌
著書で説明されている仕組みは、Step3以降のことだと思いますが、組織や人材の醸成に応じて仕組みを変えていかれたように思います。基本的な考え方は全くブレずに、しかし運用ルールなどは朝令暮改で状況に応じて柔軟に対応されています。
トップダウンからフラットな組織への移行も、常に社員1人ひとりと真摯に向き合い、その時々の、組織環境と、個人のやる気と能力を観ながらスムーズに進められています。これはすごいことです。
普通の人がワンマンで始めると、あまり人の意見を取り入れなくなります。ましてやそこからフラットな組織に移行することはさらに難しくなります。一度形を作り軌道に乗ると安心して部下に任せ社長は次の拡大路線に興味が移りがちです。部下達も自分の居場所を固守しがちです。
立ち上げ期のみ何でもかんでも社長が指揮されたのかもしれませんが、その間も素晴らしい人間力で役員や社員を指導育成しながら常に一歩先を見据えて指揮されていったことが見て取れます。
注)自己効力感とは「目標を達成するための能力を自らが持っていると認識すること」
コミュニケーションは社員教育
社員とコミュニケーションを取ること自体を社員教育ととらえ、「真面目な私語」や「仕事の雑談」も推奨。社長自ら社員1人ひとりに話しかける。机に座って勤務中の社員に社長が立って話しかけるときは、話しかけられた社員はわざわざ立って対応しなくても良いルール。
また、「社長室もなくすべての部署が仕切りのないワンフロアに集まっていて、部署を超えて常に自由な会話ができる」環境は、セクショナリズム解消にも役立ちます。
週報で会社の理念の浸透
社員全員が毎週業務報告を書く。最初の3年間は社長がすべてのメールに返信をしていたが、今は役員が返信。経営理念や経営方針に関わる内容については、社長も対応(全社員にCC)する。
また、会議は社員教育の場であり、社長の広報活動の場でもある。「こういう会社にしたい」「こういう社員になってほしい」という「社長の思い」を浸透させることが社員教育の本質。
「社長が大切に思っていること」が伝わり、会社の理念が浸透します。経営理念が絵に描いた餅にならないよう、常に日常の行動、細かな業務上の判断においての指針として参照しながら見本を示すことは最高の現場教育です。但し、これは諸刃の剣であり、社長や役員が「背に腹は代えられない」と言い訳しながら経営理念から逸脱した行動を取れなくなります。
本気で良くしようと思うのなら、すべてを開示する覚悟が必要です。その覚悟がないのなら中途半端な改善活動は効果が出ないのでやめた方がいいでしょう。
2種類の社員教育
社員教育は①「会社の中で、仕事を通じて行う教育」(お金をかけない教育)と、②「社外で受ける教育」(お金をかける教育)がある。
①は社長が直接社員を教える「社長塾」と定期的に行っている週次/月次会議。②は社外研修や海外出張。海外出張を経験した分だけ社員が成長すると考え、事務系社員も海外展示会等に行かせる。
私も外資系勤務時代、海外出張に若手社員を連れていっていました。いつもやり取りしている米国本社の開発者達と直接会う機会を作ることが目的でしたが、一度経験した若手社員は後のやる気や積極性が全く違っていました。私も初めて海外出張したときは、今までの価値観や人生観が変わってくるくらい新鮮な経験でした。コスト削減の一環で今はなかなか難しくなったようですが、私にとってはかけがえのない経験であり、会社には感謝しかないです。
自己組織化の推進
どうしたら社員が自発的に仕事をするようになるか?トップダウンでは組織は成長しない。「自己組織化」、自立した社員が創造的な活動をして、変化に対応できるチームにすること。上から押さえつけられることがなければ、社員は自発的に仕事に取り組む。
社長への報告は事後で良いので、自分で決め行動する。また、評価欄に「社長や役員に異論があるとき、臆せず自分の意見を言える」という項目があり、自分の意見が言える人を積極的に評価する。
最初はトップダウンで立て直しを行い、徐々に社員の自立化を促していった工夫がこの記述から見て取れます。
一般的に、社長が「自分の意見を言っていいんだよ」と言っても、建て前かも分かりません。途中ではしごを外されるかもしれません。「最初は応援するよ」と言っておいて、途中で役員達からの反対があって形勢が怪しくなると「見える成果が出ないんじゃ、俺が支援してやるのももう限界だ。」とか言われたら「もう言われたことしかしないぞ」という気持ちになりますね。
近藤社長の場合、とことん本気なのが分かります。評価欄にも書いて実際に評価し、社員の前で社長の批判をした社員に、「気づかせてくれて感謝する。」とまで言ってます。ここまでされたら、社員は自発的に動き出すでしょう。
どんな理由があろうと「赤字は犯罪」
・社員が努力すれば利益を生む構造をつくるのが、社長の仕事。利益は「雇用を守るため」に必要であって、利益を上げること自体が目的ではない。しかし、「人を大切にするから利益は二の次」ではなく、「人を大切にするからその前提として利益が必要」。
・また、売り上げ目標に期限は明記しない。会社を大きくすることに意味はない。売上目標に「いつまで」を明記しないのは「社員に対する私の覚悟」の現れ。大事なのは、社員に「働くことで得られる喜びを提供すること」。
この書籍を著された時期はまだ欧米のティール組織の存在がご存じなかったようです。しかし、上記表現は、ティール組織のCEOが言われている言葉そのものです。
従来ながらのピラミッド組織から、いきなりティール組織に移行するか、日本レーザーのようにワンマン社長が経営を立て直した後に徐々にフラットな体制に移行していくかは状況に応じて様々です。しかし、共通しているのはトップである、CEO、社長がティールパラダイムの視点で、全くブレずに行動されていることです。
クレドをつくり、経営者、社員両方に守るべき約束を明確にしている
クレドとは、「経営理念、ミッション、価値観、経営方針などを言明したもの。社員にとっては社員憲章や行動規範に当たる」。いわば「働き方の契約書」。常にクレドの冊子を持ち歩き、会議の前後に唱和。内容を人事評価の項目にも反映させている。
日本レーザーが他社の経営理念と大きく違うのは、
①会社は、社員の雇用と成長の機会を守るために存在している
②会社は、社員を幸せにするために存在している
他社と大きく違うのは、経営理念と照らし合わせて、日々の行動の指針や評価基準としていることです。「こんな時はどうすればいいか?」という日々の判断の一つ一つに答えが出せます。
これはすごいことです。ここまでホワイトな企業にいたことがないので正直完全に想像出来ないのですが、もしこんな会社に在籍出来れば、人生の悩みの半分以上は解決してしまいそうです。「会社から見て、自分の存在価値はあるのか?」いつも溺れないように必死で泳いでいる気持ちで会社員時代を過ごしてきました。とことん信頼できるこの会社に在籍する限りは、身体が動かなくなるまで会社に尽くせばいいのですから。
262の法則の下の20%の社員を切らない
下20%を辞めさせると、残り80%の社員のモチベーションが低下するから。自分がもし下20%に落ちても会社は守ってくれると思えれば、会社に貢献する。
決して甘い対応をするのではなく、評価は公平にされるようで、その結果は厳しく給与に反映されます。ただ、本人が居づらくなるような様々ないやがらせは一切ないと想像します。
ブラック企業では、個人成績を貼り出したり、成績の悪い人を識別できるタスキを付けさせたり、下20%のやる気をなくさせ追い出す作戦かもしれませんが、そんな職場では常に残り80%もやる気を無くして辞めているので常に募集をかけています。
アリの実験では、下20%を抜いても、今度は残り80%の中で下20%が働かなくなるというのが自然の法則です。下20%を手厚く扱うことが理にかなっていることを認めるべきです。
給料が安くても社員が辞めない3つの条件
①言いたいことが言える明るい風土がある
②社員が会社から大事にされていると実感している
③会社は自分のものだという当事者意識を持てる
社長は、社員から面と向かって批判をされても、恥をかかされたと思わず感謝し礼を言う。
このあたりの近藤会長の人間力が凄すぎて、普通の人は真似できないのかもしれませんが、「給料が安くても辞めない環境」はこれからの日本企業で目指す方向ではないでしょうか?ひと昔前の京セラや松下のような組織環境(お金より生き甲斐。給料は低いが雇用を保証する。)を取り戻せないのでしょうか?
各自が自分の目標を目指す健全な競争
同僚同志が互いにライバル視して競争するのではなく、「おぬしやるな」と互いに認め合う雰囲気を作る。実質的に社長&役員と社員の2階層のフラットな組織で、各自自己完結型の業務スタイル。
この記述もティール組織の価値観です。競争ではなく、自分の内面にある指針に従って生きるのです。同僚との競争、勝ち負けの感情は「恐れ」から来るもので、自分の心の空虚さを埋めようとする感情から来ています。
新卒一括採用をやめて通年採用にする
新卒採用では採れない優秀な人材がやりがいを求めて応募してくる。雇った以上は仲間として全力で支援する。そうできないと思える人ならば、最初から受け入れない。
この記述もティール組織の価値観そのものです。採用前に十分自社のカラーに合っているか?自社の理念に沿って行動できるのかを確認し、お互い納得して入社します。
透明性の高い人事制度をつくる
公平に評価するために役員全員が全社員の評価をしたあとに、社長とともに長時間(開始当初は一泊二日)論議し、役員間の基準や価値観の調整を毎回行う。
優秀な人材が多くいる巨大企業と違い、中小企業はキーマンが実権を握っている場合が多々あります。評価者の間で価値観のすり合わせをしておく必要があり、社員が間違った方向に大きく外れる前にきっちり軌道修正をする必要があります。そしてどうしても合わないのなら、去ってもらうしかないでしょう。
まとめ
とにかく信じられないくらい社員を大切にしている社長なので、逆にティール組織導入時の参考事例になりにくいように思いました。他の役員や社員の方々との交流も書かれているのですが、やはり抜きん出て近藤社長が優秀で奉仕的精神で、常にご自分が先頭切って苦労されているので周囲も追随するのでしょう。
中小企業でティール組織を導入しようとお考えの方は、今回お勧めした書籍をぜひ読んで頂き、「単に仕組みを真似る」のではなく、「自分が目指しているもの」をもう一度よく確認してください。
状況によってはワンマンでどんどん進めていっても、社員を大切にしていれば従ってくれ、やがて時期が熟せば自発的に動くフラットな組織に変えていけばいいのです。
私が今回の「ありえない~」を読んで感じた、小さな組織をティール組織にうまく変容させるコツは、最初からチームを作らず自己完結型の個人の集まりの組織を作ることです。社長の負担は非常に重いものになりますが、間に役員や幹部や間接部門の意思を入れず直接社員とコミュニケーションを取ることが、社長の想いを正しく伝えることになります。まずは階層を無くすところからスタートです。
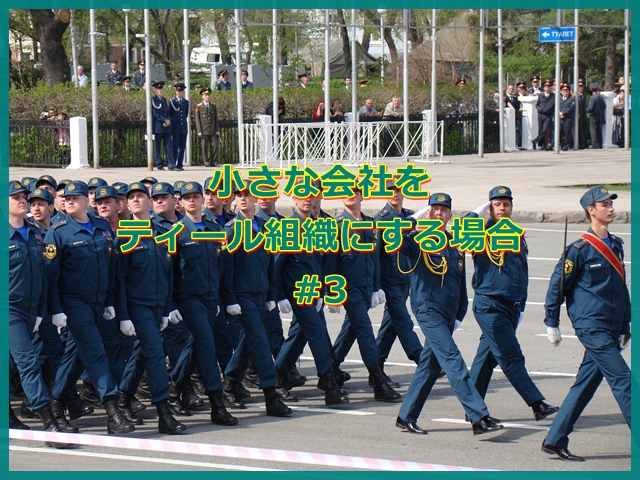
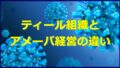
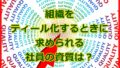
コメント