1.リーダーのマネジメント力で始めるか?しくみから変えていくか?
前回は会社の悩みからオレンジ組織の問題を下記のように推測しました。
①現場でOJTできる環境がない
②マネジメントがプアでやる気を削がれる
③中間管理職の負荷が重すぎる
典型的なティール組織にしてしまえば、すべての問題は解決します。特にスタートアップのソフトウェアー開発の組織には最適と思います。
ただ、立ち上げ時の混沌とした状況からうまく抜け出せず空中分解してしまう可能性もあり、とても歴史ある会社では始められないのが現状です。人事や研修部門がコーチングなどを社内研修に取り入れても、現実とのギャップから何の効果も得られないのと同じです。教室でいくら学んでも、現場の仕事で使えないと意味がありません。OJTで応用し、現場で実践できることが重要なのです。
現実的には、あくまで既存のオレンジ組織のままで、重要ポイントに意識しながら、少しずつ社員の意識と仕組みを変えていく方法が無難です。
改革を任せられる現場リーダーが不在のときは、ピラミッド組織のまま、社長(もしくは事業部長クラス)自ら指揮し、リーダー育成やコミュニケーション改善から始めます。(=リーダー主導型)
任せられるリーダー達がいれば、彼らを信じ、ティールの環境を実験的に行います。(仕組み先行型)
ティール組織、オレンジ組織共通で組織マネジメントを上手く運営させる重要ポイントが5つあると前回書きました。
①人を大切にする
社員を甘やかすことではありません。全員の意見を聞いて回るわけでもありません。人として対等な立場で相手のことを思いやることです。
②基本的な行動ルール(価値観、倫理観)を決める
社会人として常識的な振る舞い、コミュニケーションの取り方、挨拶や会話の仕方です。
③実務上のルールを決める
人と協力して気持ち良く作業が出来るマナー&ルール、仕事を段取りよく行うコツ、問題を煙が出る前の予兆を感じ取る仕事の感性、等の共有、伝承を意識した振る舞いの仕方です。
④環境を整える
予算申請や稟議を不要にする小グループ毎の自主経営(全社員で意見交換でき、必要な情報を共有できるインフラ。必要最低限のスタッフ部門)
⑤牽引するリーダーが必須
リーダーが全責任を持つので社長代理のような立場になります。
この5つのポイントで説明していきます。
2.リーダー指導型
社長(もしくは事業部長クラス)自ら指揮し、リーダー育成やコミュニケーション改善から始め、
立ち上げは、ややワンマンのリーダーシップで行います。社長の意思を伝え、具体化を社員と一緒に考えていきます。全員参加の会議で業務全体の流れを共有し、別に小グループで業務進捗会議を行います。
会議は実務と改善活動を平行して行い、改善活動をスタッフ部門(人事、業務棟)だけが担当することは絶対に避けてください。
効果的な会議の工夫が必要になり、自分が担当した業務報告を事細かに説明して会議時間が4時間に及ぶ、とかを防ぎます。
ここで一番重要なのは、リーダーの能力です。ピラミッド組織は上から命令し言われたことを実行するには最適な組織です。その利点を利用し、最初に大きく意識改革をしてしまうのです。但しそれはリーダーの押し付け的部分もあります。改善活動が進むにつれて、その部分を修正し、社員が自発的に動けるようにブラッシュアップしていかないといけません。また、頭で理解しても身体が付いていかず見える成果が出るのが遅い時期が必ずあります。そのときに、リーダーがしびれを切らしてまた最初のワンマンに戻ってしまわないように気を付けないといけません。
①人を大切にする
利益が出なければ会社は存続できません。ある程度以上儲けないと理想の環境も継続できないのです。その妥協点を考えます。
社内プロセス、評価基準等に矛盾するところがないか見直します。仕事の出来ない人をクビにするのか?優秀な人を外部から調達し、人間的に問題があっても我慢するのか?サイコパスで仕事だけ出来る人を使い続けるのか?能力は低くても自分で出来ることを探して頑張っている人をリストラするのか?本音で考えて、必要なら評価基準も変えていきます。ノルマ未達の仕事が出来ない人に見せしめ的なことをして、本当に本人はやる気が出るのでしょうか?会社の方針で成績が悪い人は自ら辞めるように仕向けているのなら、それはそれで会社の方針に沿っていればいいのかもしれません。(個人的には嫌ですが)こういった今までうやむやにして、「当たり前のこと」でごまかしてきたことを真剣に考えます。
②行動ルール
社是や社訓と重複しますが、現場で尊敬されている社員はどんな振る舞いで尊敬されるのか、こんなときは彼らならどうするのか?といろんな場面で考えて、みんなで話し合い文章化していきます。
③実務の行動ルール
仕事を迅速に、正確に行い、周囲を巻き込みOJTも兼ねた仕事の仕方をイメージして考えていきます。ベテランのノウハウを可視化継承し、効率を上げ、問題を未然に防ぎます。
④環境を整える
スタッフ部門をシンプルにして現場ですべて出来るようにすることがゴールです。採用と解雇、評価、報酬、購買などです。
3.仕組み先行型
現場で任せられるリーダー達が育成されていれば、彼らを信じ、ティールの環境を実験的に行います。改革のリーダーは社長(もしくは事業部長クラス)が責任者として指導し、15~20人のチームに分け、各グループにリーダーを配します。
リーダー育成のOJTを兼ねて彼らを信じて任せていきます。最初は戸惑い、会社として許せる範囲を下回っていたら、最初は改革のリーダーがサポートしながら進めます。
1チーム当たり15~20人のチームによる自主経営が機能していた。1つの現場で働く従業員の数を300~400人(15~20チーム)程度に制限しようとした。従業員がお互いに顔と名前を一致させ、同僚の誰とでもフランクな話し合いができる、いわば自然の限界がこの程度だと感じていた。
(ティール組織 英治出版 P147より引用)
主な会議体は、改革のリーダーと各チームのリーダー達が話し合います。それぞれのチームで行っている改善活動の情報共有を行い、良いアイデアは全グループに広めていきます。
ネットと使ってフランクな情報交換を行います。
権限の委譲については、活動の進捗状況に応じて準備進めていきます。何か問題が起きれば、改善していき失敗や変更を恐れない。
5つの重要ポイントは前項とほぼ同じです。内容に応じて全員参加とグループ毎に打ち合わせるよう使い分けます。
4.ティール組織の形に拘らなくても良い
まとめると、
リーダー指導型:
・やる気があり並外れた統括リーダーの技量が必要
・スピード感があり、失敗が少ない
・途中で社員の主体性を育むのが難しい
仕組み先行型:
・どこまで実験的に行うのか進めながらコントロールする必要がある(やる気を削がないように)
・試行錯誤の期間にうまくサポートしないと空中分解の懸念あり(先行学習したサポートチームが牽引)
・乗り切れば社員の自主性が飛躍的に伸びる
5.理想の環境=楽な環境ではない
社員のストレスは下記のように改善されます。
・現場でOJTできる
グループ内で解決できなければ、別グループに聞く。必要なら外部に依頼できる。あくまで自発的な活動だが望めば得られる環境です。
・マネジメントにやる気を削がれることがない
自分自身が経営者の目線で見て行動できることが前提だが、他人に指示されることは少なくなる。
・中間管理職が存在しない
上司部下の関係がなくなる。甘えが通用しない。他人から責められることはないが、自分で自分の取った行動や成果に責任を取らないといけない。
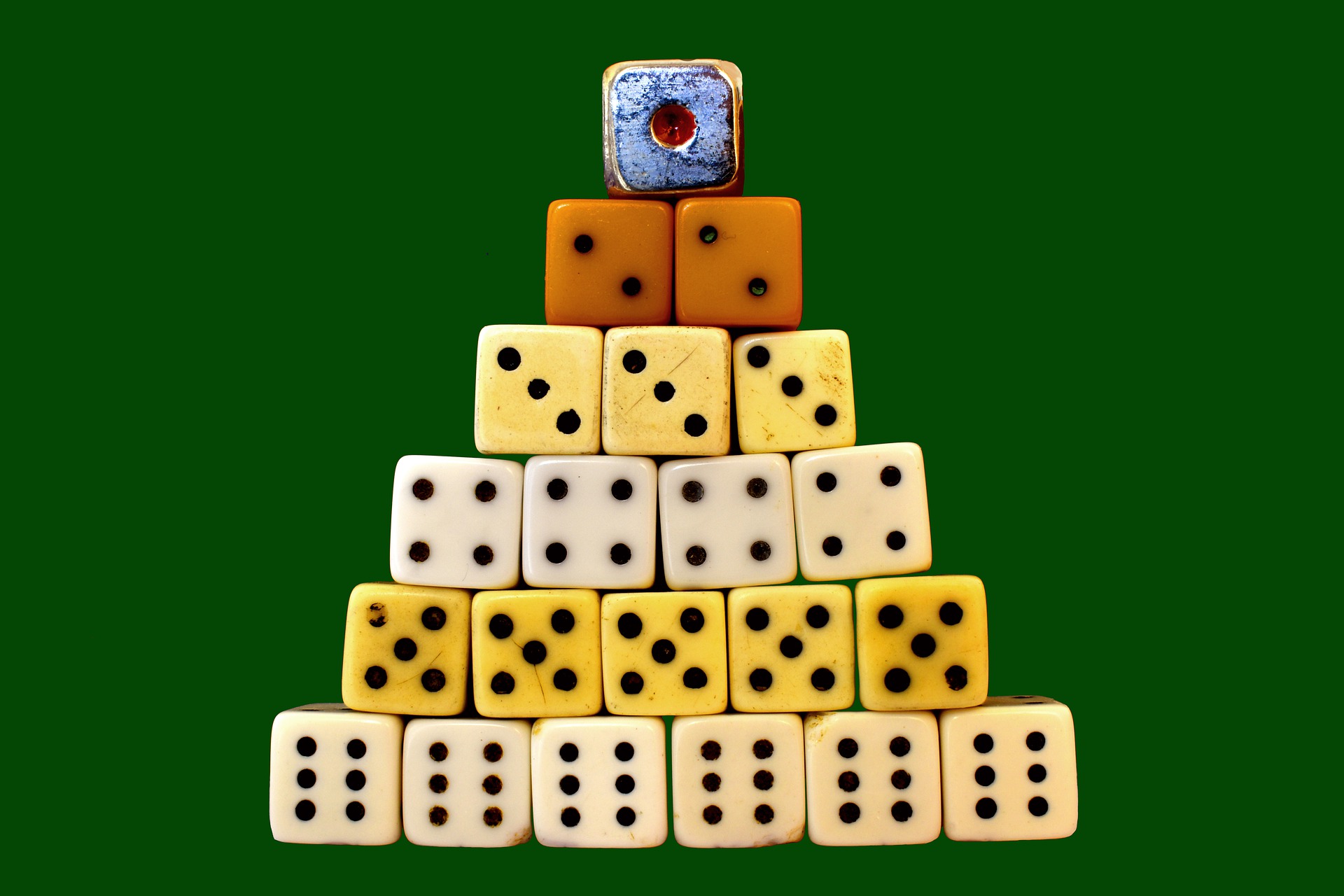


コメント