1.優良企業が前向きな目的で組織改革を実施
地元で優良企業として有名な、ある製品セグメントで世界No.1のシェアーを持つ会社で組織改革を行ったときのことです。複数ある事業部の一つが別事業部に吸収合併するタイミングに合わせて、組織を刷新し、最大顧客だった欧米巨大企業に振り回されないプロダクトポートフォリオマネジメントができるようにすることが目的で始まりました。
元々大学院卒の優秀なエンジニアが多く、ヒット商品を開発すれば40代で役員にもなれる成果主義で社員の平均収入も高いと有名な企業でした。
いろいろ社員からヒアリングしてみると、やはり不満点は出てきますが特に致命的なものはなく、下記のような点が挙げられました。
① 次の世代の開発リーダーが育たない
② 顧客ニーズがつかめない
③ 開発者同士の技術的ノウハウの情報共有、有効利用ができていない
④ いつも会議や目先の緊急業務で翻弄され、じっくり考える本来の仕事をする時間がない
⑤ 様々な名目の会議が多すぎる
私が感じたこの企業固有の特徴は下記のとおりです。
① 技術力、人事評価システムは先進だが、マネジメント力やコミュニケーション力が大きく劣る
② 変化を好まず指示待ちの社員が大部分であり、彼らの居場所もある
③ 開発営業サービス部門だけでなく本社機能スタッフも個人で動いている
規模は大きくても、組織風土はベンチャー企業に似ていました。
2.2つの事業部で明暗が分かれる
早速2つ(元は3つ)の事業部の主要メンバーを集め、一番要望の多かった事業戦略の立て直しから活動を開始しました。
その活動を通して、営業やサービス部門と開発部門が共同で考えることで、コミュニケーションの改善も思うつもりでした。ヒアリングでも多くの社員から問題として挙がっていたが、いつも下位に位置していたのが下記のコミュニケーション関係の問題でした。
① 会議がダラダラ長い。意見がまとまらない。人の話を聞かず話したがる。
② プロジェクトリーダーごとに情報管理ルールが違う。
③ 部下の管理や指導を嫌々やっている(本来マネジメントをやりたくない)
事業戦略を半年ぐらいで完成させ、次のステップに行こうとしたのですが、なかなか進まず1年近くかかりました。その内容も完成度が低く、あと3回ぐらいやり直さないといけないような出来でした。
出来の遅さに、別役員が別の企画を立ち上げました。一つは部課長クラスを集め、技術情報の共有を目的とした会議を開催。もう一つは若手開発者をグループに分け、開発業務を共有可視化する研修です。
「事業戦略を作成する作業を行いながら、実務を通して不足スキルを補い組織改革を加速する」試みはこの事業部では中止となり、もう一つのこじんまりとした事業部でのみ継続されました。
2年後、実務を通した改善活動を継続した方の事業部は主要メンバー達で自立的に打ち合わせ、決定するスタイルが習慣化し、組織内メンバーも入れ替わり雰囲気も大きく好転し、結果として売り上げは上がりました。
実務と研修を分けて進めるスタイルを選んだ事業部は、一部のリーダーのみ伸びていき、組織内の雰囲気を変えることはできませんでした。
3.成功の理由
それぞれの事業部長に聞くと、活動を継続したこじんまりとした事業部は「みんなの想いが一つになった=成功」、事業戦略を作成した事業部は「やりたいことはいろいろあったが予想以上に時間がかかった。使いこなせなかった=失敗」という感想でした。
この会社の組織風土として本質的に持っている長所短所のうち、「会議がへたで人の意見を聴かない。」については、少なくとも前者の事業部はかなり改善されているように感じました。
やはり短所は簡単に改善されないので、時間がかかります。ただ実務から乖離した環境で研修を受けても、実践で使いこなせなければ意味がありません。基礎は研修を受けて学べても、応用するには実践で使わないと上達しません。実践で不足している部分を後で勉強して埋めていくことが大切で、実務からかけ離れた知識は邪魔になるだけの場合もあります。
成功した事業部は、規模がこじんまりとしていたので実務を通して、組織改革を進めることができたのです。失敗した事業部は、2つの事業部合併と事業戦略の作成に合わせて根本的な欠点を補強しようと急ぎ、無理をしたことが敗因です。サンプルプロジェクトとして規模を小さくするか、期間をもっと長く取ってじっくりやれば成功したと思いますが、経営陣からのプレッシャーがありやるしかなかったのでしょう。
4.この事例からの教訓
頭で理解できても、自分の体に馴染ませるには時間がかかる
とびきり優秀な開発者として評価されたからこそ、若くして事業部長(兼役員)になった方なので頭では理解されていたが、現在進行形の業務とのバランスを取ることはさすがに難しかったようです。頭で考える2~3割の軽い負荷で進めた方が結果的に早いようです。
いきなりオレンジ組織からティール組織への組織変更は難しい
成功した事業部はもともと組織形態がシンプルで、グリーン組織に近いものでした。対して失敗した事業部は、狙い市場そのものが多くの別市場からの参入企業が多く混沌としていたせいもあり、多くの優秀で個性的な社員がいて競争組織(=オレンジ組織)でした。組織改革の活動をしていても、前者の事業部の社員は心の問題について関心を示し、後者の事業部の社員はスキルや論理的解決方法に興味を持っていました。
オレンジ組織でないと機能しない理由がある場合は、スタッフを入れたマトリックス的組織にして社員の負荷を減らし業務内容も見直し、グリーン組織的なマインドを少しずつ取り得れることから始めないといけません。慈愛の精神を植え付けるのではなく、オレンジ組織における利他主義(合理的自己主義)を学ぶのです。
経営陣とのコミュニケーションは密に行い、別活動と整合を取っておく
何とか社長や経営陣の了解を取って活動を始めても、完全に信用されたわけではない場合、知らないうちに別のリーダーを立てて別の企画が始まることはよくあることです。どちらが正しいとか、どちらが最も効果的か、とかを議論する必要はありません。出来れば連携を取れればいいのですが、それも難しい場合は相手を否定せずに共存の可能性を探しましょう。
5.反省点
今回は、社員のコンピテンシーが似通った社員が多く、かなり個性的な組織風土の会社でした。その良さを殺さずコミュニケーションスキルを向上させようとしたのですが、思うように効果が出ず焦りました。なまじリーダー達は地頭の良い人達ばかりだったので、手本となる先輩もいない状態で真剣に理想の組織を考えて頂き、大変だったと思います。
この後、不足しているリテラシーの中で顕著に劣っている項目は、いきなり実務で使えないので座学の研修を改革と並行して進めることにしました。
特にコーチングは実務で全く使えないスキルなので気を付けてください。
コーチングのスキルで傾聴や違った視点から物事を考えさせるスキルは使えますが、個人の生きる目的や楽しみを現在進行中の業務に関連付けて、いきなり全社員にやる気を持たせることは不可能です。
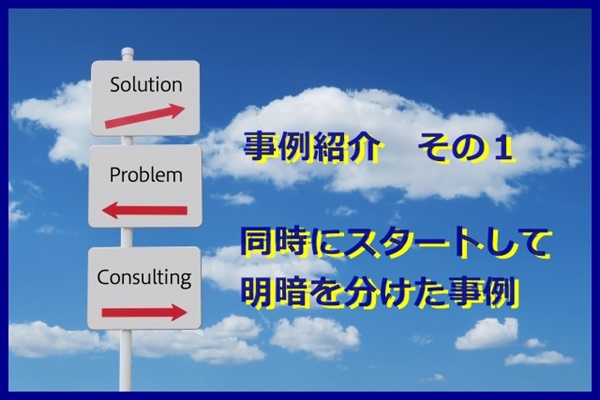
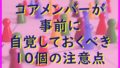

コメント