2018年に英治出版より出版された「ティール組織」は、「マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現」とサブタイトルがつけられており、最新の組織運営として紹介されています。
ティール組織の特徴
ティール組織の特徴として、自主経営、全体性、存在目的の3つが挙げられます。
「自主経営」は、社員一人ひとりが主体的、自立的に動くことです。
「全体性」とは、組織への関わり方が、給料の対価として時間と労力を提供する辛抱の場(=仮面を被る)ではなく、本音をさらけだしてやりたいことを自由に提案できる環境のことです。
「存在目的」は、オレンジ組織が「どのように利益を得るか?」「どのように事業展開するか?」と問いかけるのに対し、ティール組織は「どうあるべきか?」と問いかけることです。つまり、本質的な問いかけを繰り返すことにより、社員一人ひとりが本質を外さずに行動できるのです。
オレンジ組織で「どうあるべきか?」が語られることはありません。あったとしても本気ではなくあくまで体裁です。本音ではあまり興味のない分野なのです。
この3つが整ったときの組織は、大幅な権限の委譲により「スタッフ組織は必要最小限」「社員一人ひとりに無制限の決済権」「社員を監視するしくみや部署は不要」「情報共有の徹底と権限の分散による会議の激減」といった環境になります。
アンバー/オレンジ組織でも似た環境は作れる
社員一人ひとりの力を同じ方向に向かわせ成果を出すことは、ティール組織でなくてもできます。
アンバー組織では上位階級からの指示を出すだけ。オレンジ組織では、昇進や増収(or 降格や減収)でモチベートさせることになります。
しかし、個人人々の本心からのやる気を出させることは難しく、本人も自分は100%頑張っていると思っていても、自分が自発的に楽しんで動いている場合と比べれば頑張れていない。
想像してみてください。オレンジ組織では、常に上長に判断を仰がないといけないのです。いくら良い上司がいて社長に掛け合ってくれて許可をもらったとしても、その方法が通用するのは緊急時だけです。あまり有能でない上司の場合、どれだけ職場の日常が耐え難いものになるか。
普段は上司やスタッフ部門の審査プロセス等面倒な手続きを経ないといけないので、新しい試みを試したり、失敗することが許されないのです。何度も経験するうちに、新しい挑戦はしなくなるかもしれません。本人はやる気があっても、気持ち的に萎えるプロセスが立ちはだかり、「あんたらは仕事の邪魔をしたいのか?」と言いたくなるのです。
ティール組織では、社員一人ひとりが制限のない権限を持てるのです。別に失敗に対して制裁があるわけではありませんが、自分が全権の責任を持つということは、オレンジ組織以上に緊張し、何度も確認しないと先に進めないかもしれません。でもそれは非常に心地よい緊張感であり、やる気や生き甲斐を感じられる環境を作ります。
「お前はまだ経験が足りない。」とか言って重箱の隅を楊枝でほじくるような上司やスタッフ部門もいません。いるのは前向き、効率的に仕事をサポートしてくれる専門家たちです。社員にとって、やる気を削ぐ出来事やプロセスが全くないのです。「説明不足で予算が通らない」「毎日意味のない会議で時間がつぶれる」「情報が上層部で無駄に止まっていた」「部下の育成や評価を命じられたが、そもそもそういったことが責任持ってやれる環境でない」等やる気を削ぐ出来事が一切ない環境です。
うまく機能しているアンバーやオレンジ組織の企業は存在します。そして、それらの組織の上位にいる人々の意識発達ステージが上れば上るほど、業績が伸びる、と言われています。
このアンバーやオレンジ組織での違いはなんなのでしょうか?
私は、そこにいる社員一人一人の気持が違ってくるからだと思います。「自分は信用されていないと感じることが少ない」「やる気を削ぐプロセスや上司が少ない」「仕事を任してもらえる」「失敗に寛容で挑戦できる」「上司が信頼できる」「サポートしてくれる人や環境がある」といったやる気が起きる環境が多いのではないかと考えます。
本質的な部分では、アンバー/オレンジ組織はピラミッド組織です。上意下達のプロセスです。その中で社員が自由気ままに仕事をすることは許されません。上司の判断を仰ぎ、身の程をわきまえた処世術が要求されます。会社での仮面を被り程度の差はありますが抑圧されます。優秀なトップがこのストレスを取り除く工夫をすることで、業績が伸びていくのです。
ティール組織は、いわばストレスフリーの環境です。社員一人ひとりが自然のままにのびのび行動することを最大の目的に設計されたような組織です。一人ひとりが意思を持った細胞の集合体のような組織です。
つまり、ティール組織は、組織内の環境維持はメンテナンスフリー。しかし、外的環境から守るために社長が大変な労力を必要とします。「その組織内にいるだけで無理せず、特に優秀でなくても自然に社員のやる気が出て、その結果として利益が出る環境」です。
アンバー/オレンジ組織で社員のやる気を出す環境を作るには、優秀なトップによる細かな組織マネジメントの設計とマネジメント層への指導と地道な環境維持が必要になってきます。
ティール組織を導入するときの条件
ティール組織に在籍する社員は、特にティールのレンズで眺めること(=意識発達ステージが一段上にいること)ができなくても構いません。
ティール組織の優れた組織環境の中で働くことで、徐々に意識発達を促すこともあるかもしれませんし、特に変化なくてもティール組織の慣行に従うことでストレスなく自然にやる気が出てくるからです。
ただ、アンバー/オレンジ組織において、中間管理職の中にティールのレンズで眺めることができる人がたくさんいたとしても、その人達がいくら頑張って変えようとしてもその会社はティール組織にはなりません。万が一なれたとしても長続きしません。
つまり、ティール組織とアンバー/オレンジ組織の、一番決定的な違いは「経営トップの意識発達ステージがオレンジ組織の経営トップより一段上に進化している」ということです。
ティール組織を導入するときの必要条件は下記の2つだけです。
①経営トップがティールの世界観を養い、精神的な発達を遂げていなければならない。
②組織のオーナもティールの世界観を理解し、受け入れていなければならない。
取締役会は「理解できなくても」、ティールのリーダーが圧倒的な実績を示すと、一時的にすべてを任せる場合もある。ところが、景気が悪くなったり極めて重要な選択に迫られたりすると、自分の目に合理的と映る方法(トップダウンの上意下達式の命令や仕組み)だけで状況を統制したがるようになる。
出典:「ティール組織」英治出版 P394
「ティールのレンズで眺めること」とは?
「ティールのレンズで眺めること」とは、「ティールの世界観を持つこと」=「オレンジより意識発達ステージが上がっている」ということになります。もっと具体的に説明してみます。
「ステージを上がるのは、複雑で、神秘的で、精神的なプロセスだ。それは自らの内側から起こるもので、どんなに素晴らしい主張をもってしても、外から強制されてできるものではない。」と記述されているように、ステージの違いは生まれついてのものかもしれませんし、個人の人生経験において悟りに近い気付きがあるのかもしれません。ただ確かに意識の違いは存在します。ステージが上の人から見れば、ティール組織の環境は当たり前のことなのです。「自分の価値観に合っている」ものなのです。
ティールのレンズで見たら、合理的な組織環境は絶対にオレンジ組織よりティール組織です。ピラミッド構造のトップが仕切る構造より一つ一つの細胞が頭脳を持った組織構造の方が合理的なことは明白です。判断スピードや柔軟性、独創性、すべてにおいて優れています。人材育成においても、ティール組織はその組織環境の中で現場に近い実践的なOJTにより自由に伸びていきます。
「社員を信じること」「エゴを捨てること」についても何の抵抗も迷いもありません。それが理にかなっていて、自然で正しいことだと疑う余地もないからです。
アンバー/オレンジのレンズで見ると、社員1人ひとりが決済権限を持つことを危険だと思うでしょう。しかし、ティールのレンズで見ると、社員一人ひとりに決済権を持たせて起こる些細な問題より、権限を幹部マネジメント層に集中させる方がよほど弊害が大きく無駄に見えます。
人はピラミッド組織の階層を上り詰める過程の競争において、歪な仮面を被り下位階層を威圧し統制することに慣れざるを得ないからです。だからこそ「真のマネジメント」に習熟しないといけないのですが、周囲の腐ったリンゴからの影響を受けずに正しい発達を続ける人は稀です。自分でも気付かないうちに、権力を持たない人を軽んじています。ティールのレンズを持つ社員から見ると、それは耐え難い屈辱であり、自分の労力を搾取されているように感じられます。この「些細な感情」が原因で組織の推進力が萎えていることに、オレンジのステージの中でもさらに意識レベルが低いマネジメント層は全く気付かないのです。
オレンジ組織は、ティールのレンズで眺めればどう映るのか?
「オレンジ組織は合理的には思えない。自分の価値観だけでなく、仕事の目的や、人々がどう支え合うかについての揺るぎない信念が侵害されるから。」「自分のため、会社のためにお金を稼ぐことが主な動機づけになったことはない。」と「ティール組織」に記述されています。
エゴから来る無意味な競争、隠蔽、不正、こういったことは程度の差こそあれオレンジ組織では日常茶飯事です。社内政治に忙殺され、純粋な仕事のワクワク感を楽しむことなどなくなっています。
ティールのレンズで眺めなくても、ピラミッド組織の上位に位置するマネジメント層の振る舞いほど、滑稽で陳腐なものはありません。よくドラマで出てくる無能な上司役が演じる振る舞いである、「部下の手柄を自分の手柄にし、自分のミスは部下のせいにする」「情報を独り占めすることで自分の価値を高める」「肩書でその人を信用するかを決める」「自分の派閥でない人を排除」「上司にごまをすり、部下を厳しく叱る」等が現実の世界でも頻繁に見ることができるのが悲しい現実です。
ティール組織の職場の空気感は?
私のイメージですが、社員ひとり一人は誰からの制限も受けることなく自由に積極的に仕事を探し、探求することが自然です。そして、その結果として利益が上がります。それは他人との競争ではありません。自分がピラミッドの階段を上ることや人を従わせることには興味がありません。自分が得意なところは必要なら周囲に情報提供し奉仕します。スタッフ部門はほとんどありません。あったとしても必要最小限の専門家がサポートしています。
職場の空気感は、みんなワクワク生き生き仕事し、無理せず自然に振舞っています。自分の責任において、目一杯頑張ることもありますが、周囲にサポートしてくれる環境があり一体感があります。
私が目指してきた環境はやはりティール組織
私も幼少のときからアンバー/オレンジ組織の慣行に対する違和感を、学校教育や職場環境に感じ続けてきました。
学生時代は、指導者のリーダーシップというものへの失望感を常に感じていました。
職場ではプロジェクトリーダーとしてマネジメントをしているとき、社内での互いの存在価値を高めるための競争や駆け引きに違和感を感じ続け、ピラミッド組織の階層を上がるにつれその比率が増してくるのに組織の無駄や歪に嫌気がさしました。
社員一人ひとりが自発的に動くときに障害となるのが、権限と信頼関係です。正論で動ける場合もありますが、多くは根拠のない信頼関係で成り立っています。人はその結果獲得した権限により強引な振る舞いも許されるようになり、だんだんと感覚が麻痺し、人も組織も腐敗していきます。その腐敗を未然に防ぐために、多くの労力を費やしスタッフ部門を作るのです。
この無駄を省き、職場の空気を浄化させ、社員がワクワクして働ける環境を作れないか?
私はこのしくみを工夫し、コンサルとして周囲に説明してきましたが、「利益を上げることが第一の目的」ではなかったためか、反応は良くありませんでした。今なら、その理由がはっきりわかります。私が出会えた人達は「オレンジのレンズ」の世界観だったからです。
私は、会社員時代、現場マネジャーを経験し、いつもメンバーのやる気を出す環境を作るのに苦労してきました。一人一人の適性や意見に合わせて緻密に対応し、気持ちを盛り上げてチームとしてワクワク感、ドライブの利いたみんなで一緒に頑張っているぞ、といった一体感を出すことに専念しました。その結果、メンバーはみんな頑張り、プロジェクトは成功しました。今思えば、それは紛れもなくティールの価値観だったのです。
つまり、ティール組織の根底に流れる価値観は、欧米でも日本でも変わりなく、昔から日本でも存在したもので、最近の日本企業が忘れているものです
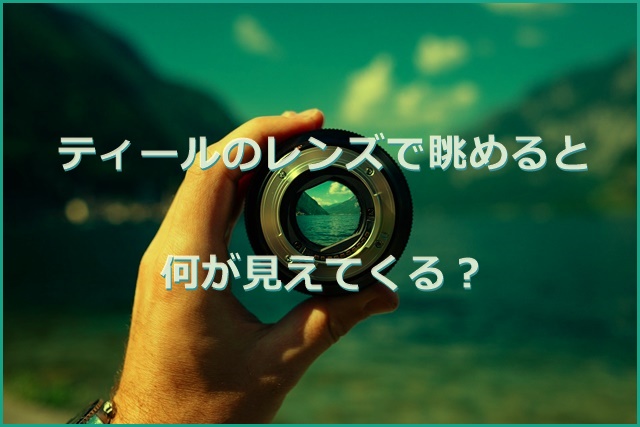


コメント