Q1: 既存の改善活動を中止することで無駄になるコストとの比較はできますか?
回答:新しい活動を開始できる時点では、従来のコスト重視の価値観から脱却でき、大枠で合意が取れていると想定しています。
逆に言えば、具体的活動を開始する前に、オレンジ組織的な、従来のコスト比だけで議論しようとする役員や社員に全体像や目指すゴールを必要し、理解と合意を得る必要があります。
成功事例を元に十分コスト的にもメリットがある予想を説明する前に、根本的に最も重視する「重要成功要因」は、売上でもコストでもない、と言い切る話し合いを最初にするべきです。
総論賛成まで合意を取り付けたところで、新規組織やプロジェクト、限定的部門で試験的に運用するか、新しいプラクティス提案等、限定的な試みで確実に成果を出しながら広げていくことになります。
Q2 : 有能な現場の社員を説得しないと先に進めないのでは?
回答:迅速に改革を進めるためには、最初から全員は無理でも現場のキーマンの理解を取り付ける必要があります。外部の識者に講演してもらっても効果は少なく、具体的に現場がどうなるかを細かく説明する必要があります。
例え、未完成の状態であっても説明に嘘や矛盾がなく熱意があれば、本当に有能な現場マネージャーなら話し合いを重ねる毎に理解してくれるようになるはずです。
限定的な成果を出していくことで段々と協力者が増え、ある閾値を越えると流れが変わり、活動が加速します。今まで様子見だった人も徐々に協力してくれます。
Q3 : 井の中の蛙的な、世間と乖離した自社の空気感を変え、危機感を持たせるには?
回答:危機感を持たせることは比較的簡単にできます。柔軟な思考の社員を選び、新組織やサンプルPjで成果を出すと、日和見主義だった多くの社員は既存の風土を全否定するようになります。
但し、急ぎすぎるとそれまで無難に運営されていた現行業務がバラバラになってしまいます。
頭で考えるだけでなく、新しい風土、思考方法に身体も心も馴染んでから、少しずつ移行させないと過度期の生産効率が落ち込みます。
頭で理解しても身体が馴染んでいない状態、メンタルモデル化出来てない状態では、現場で起こる様々な状況に柔軟に対応するだけの準備が出来ていないからです。
Q4 : 経営陣の感情的な反対を納得させる方法は?
回答:トップリーダー(創業者、社長、CEO)がこの活動の発起人で、心底から願っている場合は、役員や組織オーナーを説得することは可能です。正しく行動すれば長期的に見てデメリットの少ない活動だと自信を持って言えるからです。
それ以外の場合は、段階的に成果を検証しながら進めていき、何度もビジョンに沿ったあるべき姿を描き直し、じっくり話し合う場を何度も設けるしか解決策はありません。
従来のトップダウン的なマネジメントでは解決しないこともある、ということに気付いていて、自分の居場所が安泰であることが前提でなら、何かいい方法があれば試してみたいと考えている人は多いはずです。
Q5 : 迅速に改革を進める方法は?
回答:理想と現実のギャップを埋めていく作業の常に半歩先に、活動メンバーの育成を進めていくこと。
各自が正しい思考方法、行動指針を持って動くことで、常に突きつけられる「各論反対派」からの問いかけに、柔軟に対応していける。
時間をかけて解決策に悩む時間が勿体ない。どんどん前進する。細部に拘らず、過度に局所最適化せず、軌道修正を恐れない。
慣れないことをやると効率が下がるのは当たり前。ゴール設定は妥協しないが、極力既存プロセスに最小減の改善を加え迅速に成果が出るようにする。
何度も改善サイクルを繰り返し、ビジョン、ミッション、行動指針等の完成度も上げていく。
Q6 : 最後は全員が賛同してくれるまでやるのか?
回答:改革を進めていくと、新しい環境の元では、「水を得た魚のように活躍する人」、「最初は頭で理解し、努力して馴染ませてくる人」、「頭で理解していても身体が動かない人」、「すべてに拒否反応を示す人」の4つのタイプに分かれます。
「頭で理解していても身体が動かない人」と「すべてに拒否反応を示す人」の一部は残念ながら会社を離れることになりがちです。
Q7 : 今後増えていくテレワーク(=リモートワーク)の環境での注意点は?
回答:リアルの環境を経験した社員はテレワークでも対応可能ですが、テレワークしか経験していない新人は、経験を積みにくくなります。
それは、「些細な疑問点をその瞬間に誰かに聞いて解決しするコミュニケーションを取りにくい」、「周囲で日々起こっている同僚達のやりとりを聞いて学ぶ機会がない」、「先輩や上司が横から仕事の状況を見て随時アドバイスすることがない」といった日常の些細なコミュニケーションが少ないからです。
これを改善するには、当たり前のことと思われるかもしれませんが、上司も部下も、新入社員も、同様の「会社におけるコミュニケーションの取り方」をテーマにした、その組織独自の研修を受けるようにする必要があります。社内イントラやSNS等のツールで補完するのはその共通認識であるルールを明確にした後で良いと思います。AI化も同様です。
Q8:具体的にはどんなサポートをしてくれますか?
回答:トップリーダー(=創始者、社長、CEO)or トップリーダーの命を受けた活動リーダー、およびコアメンバー(=初期活動中心メンバー)でやれること、やるべきことや、行動した先に何が待ち受けているかを予見し、最適な進め方をアドバイス、ご提案いたします。
組織を変えようと動いたときに巻き起こる、その時々の問題や課題は、実際に経験してみないと予知できないものもあります。
プロのコンサルに依頼すると基本的に彼らは間違った解決策を提案しません。但し、彼らの提案はその会社のビジョンに沿って検討しているかは別なのです。
プロの意見を聞いて、どう咀嚼しその組織の人達自身の血肉としていくかが問題なのです。私はその作業を中心にサポートしていきます。
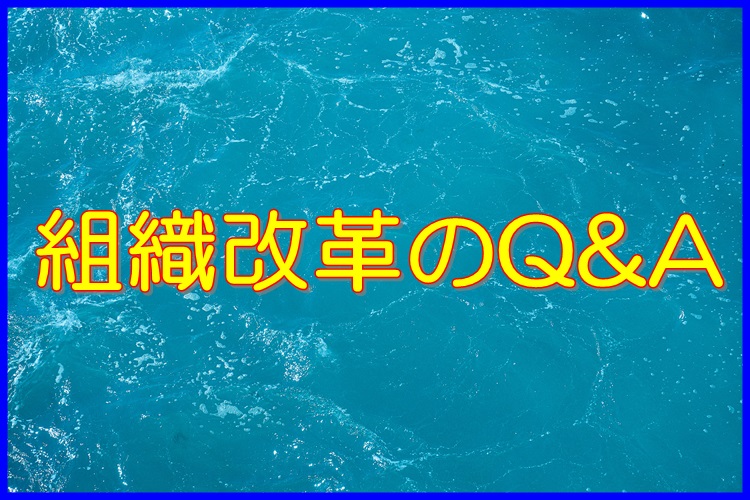
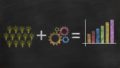
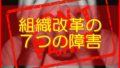
コメント