1.「ティール組織」出版前は「学習する組織」を参考に活動
2018年にティール組織が出版されてから、成果主義の弊害やどうすれば社員が生き生きと自発的に行動できるしくみをつくれるか等を説明するのが、非常に容易になりました。
キーとなるのは以前から「他人の気持ちを考慮すること」で何ら変わりません。今までは「サーバントリーダーシップ」的に聞こえる「他人を思いやる」(=他人の気持ちをおしはかって、いたわる)と同義だったので誤解されやすかったのですが、実はもっとニュートラルで合理的な理由、「人の感情を考慮して組織環境を作った方が効率が良く成果が出る」が根底にあるのです。
私が組織改革のリーダーとして活動し始めたのは2003年頃であり、当時ピーターセンゲの学習する組織を読んで勉強しました。当時、コツコツと地道な活動を行うことがどう繋がって目に見える利益やシェアに繋がるかを可視化したものが、改善活動時に採用したツールはバランススコアカードでした。バランススコアカードの長所は「トップから組織末端までの体系的な方針マネジメントが行いやすい」ところです。
本来は、業績や効率性を可視化するツールだったのですが、「学習と成長の視点」と言った可視化しにくいものや中長期視点の目標を盛り込めます。私は、社員のやる気につながる施策を盛り込むことを目的として採用しました。
つまり、ティール組織は、各チームの活動内容を含んだ全情報の共有がされており、細かな部分で活動をサポートするしくみが出来ています。バランススコアカードは社員個々人のコミュニケーション能力や組織の仕組みの不備を補い、社員の足並みを揃えるtoolなのです。
トップから組織末端までの各部署の活動が全体にどう繋がっているか?末端部署の目立たず地道な活動の成果が全体の成果にどう貢献したかを共有できるよう意識して作成しました。
このバランススコアカードを使って、営業と開発部門が共同で事業戦略を作るところから始めて、戦略マップを1年かかって作成しました。
2.オレンジ組織の眼鏡をかけた役員には成果が理解できなかった
その成果報告を経営会議で発表したときのことです。この活動を経営会議の一部の方は、「そんな当たり前のこと、最初からみんな知っている。さっさと次に進め。」と言われ、全員で共有することの大切さ、重要さを理解されていませんでした。
発表者の活動リーダーの役員は、「今まで、みんなで顧客情報を細かく共有することをやらずに上から指示されただけの仕事をしていた。全体を把握して自分で考えることができるようになったことは、当たり前のことではない!自慢できる成果だ。」と反論してくれましたが、響かなかったようです。
当時、関係主要メンバー50人以上を集めて会議を行っていたのは、全員参加のメリットとして、他チームの振る舞いを見て参考にしてほしかったからです。
バランススコアカードを運用すると、当然のことながら、トップからの方針を末端に知らせるだけでなく、組織末端に到るまでの「行動マネジメント」が必須となります。
そのマネジメントのためにも、上からの押し付けでなく、参加メンバー全員の気付きによる工夫を盛り込みたかったのです。
3.バランススコアカードの実行計画以降にホラクラシー組織のノウハウを応用
そもそも、全社展開のための「戦略マップ」をつくること自体の労力は予想以上に大変で、1年かけてやっと何とか形になった程度で、その後のメンテナンスが大変です。
ここら辺からティール組織というか、ホラクラシー組織の良いところを参考に、各職場の「職務記述書」、名前から想像する形だけの使えない記述書ではなく、業務遂行に必要なコンピテンシーモデル的なものを明文化します。
バランススコアカードの進捗報告会も、いろいろ工夫して実りある会議にしないといけないので、事前に、もしくは随時ホールシステムアプローチによるダイアログを行います。
グリーン組織やティール組織を拒絶する、生粋のオレンジ組織的思考の経営会議の方々に理解して頂くためにも、バランススコアカードを前面に出すことは非常に効果的です。この点は、ティール組織の概念のなかった2003年でも同様でした。
4.ティール色を強めると中小企業でもバランススコアカードは効果的になる
なんとティール組織は事業計画がありません。長期的な計画を立てないというわけではないのですが、絵にかいた餅でなく、日々現場が主体的に活動しているので、状況をよく知らない人向けの資料をわざわざ作る必要がないからです。実践的な行動計画はほとんどの社員が把握しており、互いにつながっているからです。
この点は、中小企業においてバランススコアカードがあまり浸透しなかったことに似ています。
わざわざ労力と時間をかけて戦略マップをつくって全社員に指示し管理しなくても、他のシンプルな方法で戦略の実行は十分可能なわけです。口頭による通達や簡単な打ち合わせで充分なのです。
これについては、バランススコアカードに問題があるのではなく、トップダウンのピラミッド組織であるオレンジ組織の問題である「トップが情報を独り占め。そして、タイムラグのある上意下達」から来る面倒臭い報告スタイルが、バランススコアカードの報告形式としてスタンダード化し、それを当たり前のように中小企業でも押し付けられたせいだと思います。
5.中長期施策(人材育成等)の実行には効果的
但し、人材育成等の時間のかかることをしっかりやることを可視化することについては、バランススコアカードは非常に効果的と思います。
但し、人事を専門に担当するスタッフ部門に任せるのではなく、現場で施策を検討することが前提です。
バランススコアカードの成功事例としてサウスウエスト航空がよく例に挙げられますが、バランススコアカードを効果的に使ったことも成功の一因かも知れませんが、そもそもの経営戦略である「従業員第一主義」や、「ありのままの自分で」「仕事を楽しもう」といった経営理念があるからです。
今ではオレンジ組織の形態を持ったグリーン組織に分類され、バランススコアカードはあくまでただのツールとしての扱いです。
確かにただのツール、ですが使い方によっては非常に効果的なツールとなります。

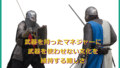

コメント