2018年にフレデリック・ラルー著の「ティール組織」が出版されて早4年が経ちます。それより前の2003年から、ピーター・センゲの「学習する組織」を読みながら現場を良くすることに注力してきましたが、なぜそこにいる大部分の人が心地良いと感じる組織が実現しないのか?苦労して実現させても長続きしないのか?いつも不思議に思っていました。なぜ心地良い環境を維持するために常に努力しないといけないのか?その原因と解決策を「ティール組織」は見事に示してくれました。
「サーバントリーダーシップ」「GIVE&TAKE」を読んで、基本的に競争好きで他人を陥れる信用できない人間が一定の割合組織に存在するのは仕方ないとしても、浮動票であるマッチャーがすべてギバー側につく組織は作れないかと考えてきた私にとって、ティール組織化することは完璧な答えになりました。ティール化した組織環境を社長が維持し続けることで、マッチャーは自然とギバーのような振る舞いをするようになるのです。これぞ組織の神髄!そこにいるだけで個人の意識を引き上げてくれるのです。
ティール組織が広がらない理由は、第一にティールパラダイムまで進化した社長が少ないこと、第二にせっかく社長の意識がティールパラダイムに到達していても、テイール組織をつくり出せず、その「リアルな雰囲気」を優秀な社員に伝えることができないことが原因です。第一の理由は仕方ないとしても、第二の問題で挫折した会社はもったいないと思います。
その挫折の原因が、もし「ティール組織とは〇〇しなければいけない」といった方法論に囚われ、やる気のある社員が疲弊したりバラバラに動いたりしたことだったとしたら・・・。
その解決策は、「オレンジでもグリーンでもなんでもいいので、目指す組織の雰囲気とはどんなものか?その空気感をみんなで共有できればいい」のです。とにかくどんどん変えていけばいいのです。すぐに完成と考えず、みんなで考えていけばいいのです。
オレンジ組織でもステージの高い人達がいる組織は、武器である権力を行使せず、そこにいる人達が心地よいと感じる環境を実現できています。グリーン組織の場合も、居心地はいいけれど躍動感やワクワク感が物足りないと感じたら、その部分を補えばいいのです。ただ、ティール組織のキモは(立ち上げ時の)互いのコミュニケーション力です。だから最初にそれが不足していると感じたらむしろオレンジ組織の改良版を目指した方が成功確率は上がります。
私が目指すティールな組織の「空気感」を過去に在籍した組織での経験談で説明してみます。
#1 良い先輩達との出会い
私が23歳のときに勤務したのは通信機器メーカーで衛星通信システムの試験調整部門に配属されました。電子回路設計を希望したのですが、配属されたのはマイクロ波の給電システムでした。最初に担当したのはL-Bandだったので試験機器も大きく長く、直径30cm、長さ2mぐらいのアルミ管を二人がかりで移動させて測定、調整を行っていました。見た目ややっていることは水道工事です。
私はやる気が出ず、1年間教育指導をしてくれる先輩のTさんにその不満をこぼしました。Tさんは入社3年目で教育指導者に抜擢された(普通は5年ぐらい)優秀な方で、私にいかに今やっている仕事がすごいことかを説明してくれました。その会社のマイクロ波給電システム(パラボラアンテナ等)の技術力は当時世界No.1で国内シェアーを独占しており、世界的に有名な設計者も在籍しているそうです。その世界一の製品を自分の手で調整し納品することがどれだけ光栄なことかを。
その話を聞いて、私は少しだけ心が動きました。回路設計に異動したい気持ちは変わらなかったのですが、世界一の製品を学びたい気持ちは出てきました。
そんなある日、過去データを探して書庫の奥で見つけた古い資料は、プロジェクトXで紹介された富士山頂レーダーシステムのデータファイルでした。1978年の二代目半導体システムです。スペクトラムアナライザの波形を手書きで硫酸紙に写し取ったデータに細かな説明がびっしり書かれていました。ついじっくり読み入ってしまい、中央研究所の高卒社員で新設された組織で、研究所を見返そうと頑張った先輩達の強い想いを感じ取りました。いつの間にか、私は回路設計部門への異動は全く考えなくなりました。
#2 自由な活動を阻止する管理職
当時はFM方式からデジタル放送に移行する直前で、まだまだFM方式の通信システムの改修の仕事がたくさんありました。衛星の中継機器(トランスポンダ)の周波数帯域を割り当てるためにL/C/Rで構成したアナログ的帯域制限フィルターが必要で、その試験調整作業が毎日山のようにありました。一つ調整するのに両手で調整棒を回し続けて延々3時間とかかかります。手先が器用でセンスが良くないとできない仕事です。出来ない人は2日ぐらいやり続けて調整トリマーを壊すまで回しても出来ないようで、30人ぐらいいるグループ内で出来るのは私を含めて3人でした。
私はもっと調整を簡単にしないといけないと思い、一旦調整完了した後に、それぞれの共振回路のL/C/Rを調べ回路諸元を調整し直して、調整箇所をセンターになるようにしました。そしてその諸元を改善提案書に書き、図面変更指示を出しました。これで次回ロットから改善されます。帯域によって違うタイプがあり、0.5MHz~36MHzまで10種類以上ありました。高周波なので製造ロットにより基盤のハンダの乗り具合で特性が変化しますが、明らかに開発時に詰めが甘かったと思われる帯域は常に苦労して調整します。設計者もそれを認めており、この機会に良くしてほしいと協力的でした。
8割方のフィルターの諸元を変更した頃、用事があって設計課に行ったとき、課長に呼び止められました。「君か、以前から勝手にフィルターの諸元を変更しているのは?あれは以前私が開発実験して諸元を決めたもので勝手に変えられると困るんだ。Qが前後しているところもあるし素人がいじってほしくない。」と言われました。「それなら開発部門で入るようにきっちり諸元を詰めてくれますね?」と言うと「当たり前だ!」と語気を荒げ不愉快そうに言われました。
Qが前後しているというのは、周波数順に共振回路の中心周波数を綺麗に並べて設計するのですが、実際は特有のリップルが発生してしまい調整できない場合があります。そんなとき現場では荒業ですがわざと共振回路を前後に交差させリップルを相殺させる場合があります。確かに諸元の追い込みが不足していることに違いないので設計者としては許せないのかもしれませんが、以前から知っていたのならもっと早く何かアクションを取らないといけないし、そもそも私に言うのではなく私の変更指示で動いてくれている設計課の担当者に言うべきことなのです。
まとめ
#1の説明
「自分がどう振舞えばいいのか」ということは、コミュニケーションが円滑に行われる職場なら、たった一人の同僚、先輩、上司からでも指針を得られます。常に回りが互いに良い影響を与え続ける環境があれば、もっと相乗効果で加速していきます。
日々どんな振る舞いをしているか目に入ってくる身近な先輩からは、非常に影響を受けやすいものです。15人のメンバーでしたが、非常に前向きだと感じたのは8人、普通が5人、反面教師的な人が2人でした。今から思えば非常に良い環境だったと思います。
設計部門(機械設計、回路設計、システム設計)、製造、工程管理、営業とのやり取りが入ると100人以上になります。これらの人もやはり比率的には5割くらいが良いと感じる人、1割弱がやや苦手~苦手と感じる人でした。ただ、大きなプロジェクトを担当して納期が迫ってくると、一つの目標に向かってみんなが協力してくれるので対応が心地良いと感じる人が7割くらいに上がってきたと思います。プロジェクトXに出た富士山頂レーダーのプロジェクトも大変だったようですが、データーファイルの資料文面は生き生きして楽しそうでした。
誰に強制されるわけでもない、一つの目標に向かって頑張ること。そして互いに必要なコミュニケーションを取り前に進もうとすること。隣のライバルと競うのではない、もっと広い範囲で、もっと遠くを見ているのです。いわば「昨日の自分」と競っているのです。こんな環境が、ティール組織にすると日常的に得られます。
#2の説明
調整部門の現場ではこのフィルター調整に手を焼いていました。特別の才能というほどではないのですが、担当させて見て5%ぐらいしかものにならないということはよほど調整が難しいのでしょう。それを改善しようとしていたのですから設計部門の担当者も非常に協力的でした。問題は設計部門の課長だけ。実は彼がそのフィルターを昔設計していたのです。私が諸元をどんどん変えているのが気に入らなかったのか、事前にお伺いを立てなかったのがいけなかったのか。しかし、当時この会社では「前工程はお客様」の標語を掲げ、我々品質部門も「たとえ一担当者でも問題を発見すれば出荷を止められる」と言われており、そのポリシーに反することは何もしていません。
新製品開発で多忙なので、古い製品の改良に時間を割きたくなかった。調整作業員が50時間ぐらい余分に作業してもその方が安い。など考えはあったのかもしれません。ただ、設計部門の課長がその理由を品質部門の新人エンジニアに説明することは決してありません。聞いたとしても、「お前が知る必要のない情報だ」と言われるに決まっています。
この雰囲気が、せっかくの職場の雰囲気を台無しにします。視野が狭く融通が利かないと評判の良くなかったこの設計部門の課長は、首にするほど悪い人ではなく普通の人でした。権力を使って強引に物事を進めるほどではなかったし。でも、こういう管理職が一番困るのです。そして私の個人的感覚ですが、5割以上の管理職はこんなタイプです。新しいことをしたがらない。事細かに説明を聞きたがる。最終ゴールの詳細な数値を要求する。
表向きは、作業者が責任を負うことがなく管理職が責任を負う形になってるから面倒なことが起きるのです。実際に問題が起これば責任者も責められるで共同責任ですが。この雰囲気が昔からきらいでした。上司がアドバイスをくれるのはいいのですが、私1人が責任を負いたかった。中途半端に口出してほしくなかったのです。ティール組織なら、こんなやる気を削ぐことはなくなります。
まとめ
競争を常に優先するオレンジ組織は、ティールの空気感を簡単にぶち壊すことができます。何よりも権力という武器を使えば何だって出来ます。その社員を辞めさせたり、その気になれば精神的に追い詰めることも簡単にできます。追い詰められた人は、心を閉じ、感度を落とし、何も発言せずに大人しくその会社で生き続けることを選ぶしかないのです。
ティール組織にすると、社員1人ひとりのコミュニケーションに関する責任は非常に重くなります。たったひとりの人間が協調性のない振る舞いをするだけで、腐ったリンゴの病気が周囲に広まります。「他人を不快にする言動」は、オレンジ組織では全く普通の振る舞いなので許されますが、ティール組織では職場を追われる直接的な原因となります。細かくその違いを説明し、入社時の契約書に明記し、「他人を不快にする言動を取った場合は辞職します」という誓約書にサインをする必要があります。
オレンジ組織を改善しようと本気でお考えなら、そしていきなりティール組織に変えるのが難しいのなら、最初に「他人を不快にする言動を取った場合は辞職します」という誓約書にサインをするルールを作るのはどうでしょうか?
事例が少なすぎて、「ティールの空気感」を伝えきれません。次回も続けて私がイメージする空気感を私の実体験からご説明いたします。
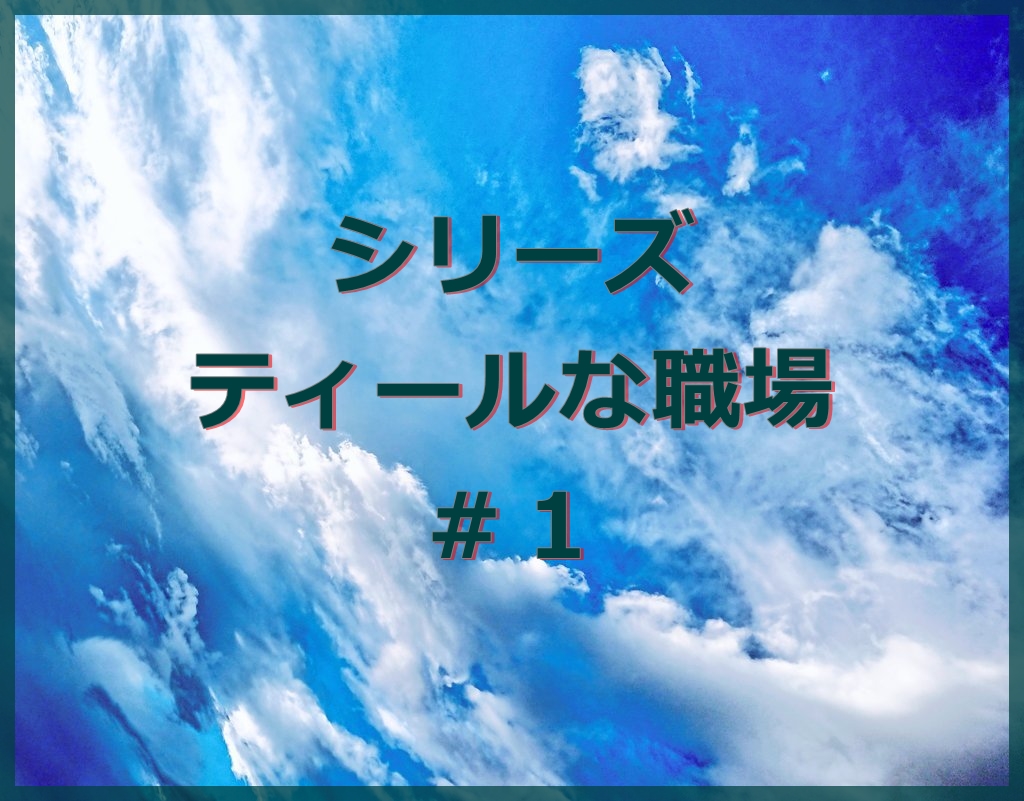


コメント