社長が社内を大きく変革しようとする場合も、社員が自分の部署の問題を改善しようとする場合も、根本的には注意することは同じです。
最も重要なのは、「自分がなぜそんな気持ちになったのか?自分を突き動かしている抑えられない気持ちがどこから来るのか?何がしたいのか?本当の目的を明確にしておくこと」です。
売上を上げることとコスト削減以外に、あまり気にもかけず軽視されたり、無視されていることで重要なことがあります。それは何なのか? 社長1人だけが考えることではなく、社員1人ひとりが考えることです。
問題や課題をどう解決していくかについては、今顕在化している問題を、どこまで深堀して原因を考えていくかで対策が変わってきます。また、改善施策についても、時間軸(納期と効果の永続性)とリスク対応(どれだけ柔軟に変化に対応できるか)を考慮します。キーになってくるのは、作業する人をどこまで信用するか(短期的に誰でもミスなく再現できるようにするのか?逆に時間をかけて習熟し、属人的に確度を上げるのか?)で変わってきます。
作業現場で重大事故が発生したケースを例に挙げて説明します。
顧客からは、至急再発防止策を提案しないと作業再開は許可しないと言われました。部長は慌てて品質部門と相談し、作業手順書に直接的な再発防止のチェック項目を追加しました。そのチェックシートを現場に配布し、再発防止の勉強会をし、やっと作業再開の許可を貰いました。
その後、また別の作業で事故が発生しました。今回も作業手順書にチェック項目を追加しましたが、顧客から許可はもらえませんでした。もっと根本的なところに問題があるのではないか?と言われ、作業リーダーの管理作業全体に見直しがされました。
パッチ処理的にチェック項目が増えた分厚い手順書を使い、ダブルチェック、トリプルチェックのためだけの作業員を余分に雇い最短期間で改善させるのか?熟練者チームによるOJTを全チーム順番に行い、基本だけでなく応用力を向上させていくのか?
これは、その組織の思想、目的によって変わってきます。ただ、後者の方がそこで働く作業員はやりがいがあると感じやすいのではないでしょうか?
下記の10項目の心得は、組織の目指す方向が違っても共通する注意事項です。
1.組織改革、改善活動はお祭りでもガス抜きの場でもなく、一番重要で基本的な実務
現在進行中の業務の問題点を洗い出し、どう改善していくかを検討する打ち合わせを開催することは、非常に重要なイベントになります。経験の浅い社員の中には、過度の期待を持って参加する人もいるかもしれませんし、過去に同様のイベントがあり特に何の効果もなかった経験をした社員は、また無駄な時間を取られるだけだと期待していない社員もいるかもしれません。
その活動のリーダーも、本音では、こんなことやっても何も変わらないが現場社員のガス抜き、気晴らしのためにやらないよりマシか、と思っているかもしれません。
実は、社員もリーダーも、ある程度空気を読んで、テーマを選んで活動します。どうせ言っても無駄な部分には触れないようにしています。この点をどこまで深堀りできるかで、社員が自分の会社をどこまで信じているかが分かります。
欧米から来たやり手の社長の改革で黒字化した巨大企業の管理職が、残念ながら現場の一人ひとりの意識は何も変わってない、とこぼしていました。
現場の改善作業のプロセス、イベントを草の根活動として捉えず、組織の重要なイベントであり、組織内を浄化させるプロセスに含むべきです。職場改善活動で挙がった根本的な問題提議が、その後ほったらかしにならずに社長まで挙がり継続的に検討されるプロセスがあるのなら、どれだけやる気が出ることでしょう。
2.俯瞰的な視点で想像力を働かせる
改善活動を行う場合に重要なのが、柔軟な想像力です。自分の部署で問題が起きても、その原因は様々な要因が考えられます。
自分の部署で再発防止の対策を検討する前に、社内、社外の全プロセスを見直します。複数の部署がそれぞれ個別に管理していることや、ミスが起こり易いボトルネックが見えてきます。全体を眺めてみてキーとなるポイントだけ管理して、後は省略します。物理的もしくはデータ処理上で出入りさえしっかり管理すれば、その中でごちゃごちゃになってプールされていても問題ないのです。安心したいから、念のためと思って無駄に仕事を作っているところを見分けます。
3.多くの情報を開示共有し、目指す最終ゴールを意識する
情報を多く持つものが力を持ち人を支配することが出来ることは確かです。しかし、組織でそれをやると、人は例え表向きは穏やかな対応であっても自発的に動かなくなります。困ったときだけ部分的に情報を開示しても、真の問題解決のアイデアの提供までには至りません。
情報を開示しない理由の一つに、自分より出来る人間の台頭を恐れているところはありませんか?例え自分が苦労して集めた情報でも公開することはさらに上を目指すためには必要なことです。教えてもらわず自分で苦労して習得することが職人の世界では重要なことと聞きます。職場によってはそのような要素の職種もあるかも知れませんが、多くの場合職場で得た情報、知識は共有し人に教えることが基本ではないでしょうか?
不要な情報を与えると勝手な行動を起こすと言う人がいますが、その懸念があるのなら情報の内容をグレード分けして、取り扱いを規定すればいいのではないでしょうか?そして、その情報の概要を公開し、仕事に必要と認められれば得られるようにするべきです。
4.現実をワクワクする楽しいものにする
自分達が過去に苦労したから、次の世代にも同様の苦労を経験させようという発想はありませんか?人が苦労して成し得た手柄を横取りする気はないが、かといってその人が独り占めするべきものではないと思います。その経験やノウハウを公開することで次の世代はもっと先に挑戦することができます。
ワクワクするような仕事とはどんなものでしょうか?過去に誰も成し得なかったことに挑戦し、苦労の末解決出来そうなヒントが閃いたらワクワクしませんか?そしてついに結果を出す。過去にそんな経験をしていたら、その人はまた困難なことに直面したくなります。その苦労の先のワクワク感や喜びを知っているからです。
人から指示されてやる仕事より、自分で選んでする仕事の方が楽しくやりがいがあります。人から指示された場合も、積極的に動いていけばどんどん面白くなってきます。
勿論長期的に考えて、これでいいのかと悩むことはあると思いますが、短期的には迷わず、責任を転嫁せず、一生懸命に生きることです。もし全員が日々平常心でこの気持ちを維持できれば、組織改革を行う必要もなくなります。
5.疑問や違和感をそのままにしない
就職した最初の会社で学んだことが、違う会社に転職して全く通用しないことがあります。
私は5回経験しましたが、前の職場で当たり前と思っていたことが、実はすごく社員にとってありがたいことだったと実感したことが何度もあります。
「前の会社ではこうだった。」と新しい職場で言うことは禁句ですが、実際ものすごく違和感を感じたり、こんなことでいいのか?と疑問に感じることが良くあります。私の場合3社目までが外資系、もしくは海外中心の事業部だったので4社目の日本企業に転職したときの違和感がすごく、明治時代に戻ったような感覚がありました。今から思えば、その違和感が原因で常にイライラしていました。前職の同僚達と比べて自分が取り残されたような気持ちになったのです。私の場合はその会社の価値観や風土と全く合ってなかったようです。
日々日常に疲れて心の感度が落ちてしまい、漠然とした気持ちの落ち込みや焦燥感で一杯になったとき、少し気持ちを落ち着かせて考えてください。自分の心のマイナスな感情はいったい何から来ているのか?何に対しての感情なのか?それを明らかにできれば、目の前のやりたくないことも、少し違った気持ちで見直すことができるかもしれません。
6.従来のしきたり、風土を否定しない
何か根本的な問題があり大きく組織を変えないともう先に進めないと感じたときでも、その会社の長年のしきたりや風土を否定してはいけません。
私は4社目の会社で組織改革のリーダーを依頼され、根本的な変革を指示されました。私自身もその会社の風土は嫌いだったので、望むところと急激な変革を推し進めました。指示された納期に間に合うよう計画を立て、支持頂いた複数の役員もがんばって頂けました。
しかし、結果は多くの社員が「頭で理解できても、体がついていかない状態」だったのです。別の幹部の提案で、納期を決めず若手人材育成の研修がスタートし、「のんびり」いく方向に軌道修正されました。
その結果、予定された期限までに目標に達することはできませんでした。長年の仕事で身に着けた反射神経的行動(=メンタルモデル)を書き換え、実践で使えるようにするには2~3年かかるようです。その間、大きく戦力ダウンするような組織変更は控えるべきです。最終ゴールを見据えて、途中従来のスタイルを継承しつつ、1~2回の中継点を作ればよいと思います。
7.業務の完成度が一旦落ちることを覚悟する
前出の理由(メンタルモデルの再構築)で予想以上に戦力が落ちます。従来の価値観を変えようとしているのです。ただの組織変更ではありません。頭で理解しても、日々の業務での応用が利きません。すぐに古い習慣で行動してしまいます。
事態を静観していた役員達も、「こんな簡単なことをするだけで、大変な時間がかかっている。何をやっているんだ!」と、すぐに結論を出したくて、改革は失敗だった!と大騒ぎします。
確かに改革活動に積極的に参加していない管理職の方で、自分の部署だけの完成度をひたすら高めるのが好きな方は、この状態が大嫌いなのです。以前はすべての業務に習熟していて、何を聞かれても対応できていたのです。改革過渡期のドタバタで、各自が想像力を持たせて頑張っているなかで、自分だけ取り残されると危機感を感じるのかもしれませんが、よく大騒ぎします。
「今まで俺が作り上げてきた部署が、ガタガタになった!」
誰も責めないから安心してくださいと、最初に何度も詳しく説明しておきましょう。
8.頭で理解できても身体が付いて行かないことを自覚する
この状態は、何度説明しても事前に想像することは難しいのです。特に、他人の気持ちを察して、しっかり傾聴してコミュニケーションしたことのない人には無理なようです。
ここでもメンタルモデルが重要になってきます。メンタルモデルとは、個人が現実世界をどのように認識し解釈しているかの認知モデルのことです。欧米人は「会議で何も発言しない人」は、本当に何も意見のない人と即座に認識します。意見があるのに様子を伺うとか、意見はあるが指名されるまで黙っている、と思って行動している人に過去会ったことがないので理解できないのです。相手の気持ちを推し量る能力はあっても、いつもじっくり観察して思考しているわけではないからです。自転車の運転に似ていて、体に染みついたメンタルモデルは脳を通さずに体が勝手に反応します。
今までの経験から自然と体に染みついた「思考のくせ」であるメンタルモデルは、真面目に話し合って確かめてみるとみんな微妙に違います。面倒ですが、一人ひとりの違いを明確にする必要があります。
そして作り上げた新しい価値観に沿った、メンタルモデルをまなび、各自の体にしみ込ませる作業が必要になってきます。
9.一番大切なのは現場の気持ち
その会社が目指す方向はリーダーである社長が決めることになりますが、詳細化は全社員で行い、変化に敏感な現場が随時微調整を行うべきです。
マネージャーを排し、上下の区別なく各自が仕事に責任を持つことは理想のスタイルです。そして、ピラミッド組織のままでも、上下の階級による不具合を極力減らした組織も多く実在します。
組織形態が重要なのではないのです。「いかに現場で働く人がやる気をそがれないか」が一番重要なのです。
10.揺れ戻しを覚悟する
組織改革を行うときに、ある一定の割合の人が賛同しだしたら、一気に風向きが変わる時があります。そして大きな成果が出て大成功!と言いたいところですが、最初は苦労して頑張った主要メンバーだけが判る小さな成果しか出ません。表面的な数字はむしろ改革前より悪くなってます。
活動に協力して頂いたお客様が「頑張ってるね。もう少しで数字が出るね。」と言ってくれる程度です。こんなこと言ってくれれば、大成功です。
ほとんどの場合、すぐに良くなると思っていたその他大勢が「これだけやっても大して変わらないのは、改革が間違っているんじゃないか?」と騒ぎ出します。
これは正しいプロセスです。慌てずに粛々と次のステップに行きましょう。

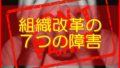
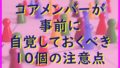
コメント