これから説明する10個の注意点は、当たり前のようですが大切な項目なので活動途中でも確認しながら活動してください。
活動リーダーが社長であり、実質的リーダーを兼務している場合は全く問題ないのですが、役員や部長クラスに活動を依頼している場合は、発起人の社長が取り残される場合があるので気を付けてください。活動途中で社長に意見を言いにくいとは思いますが、大きく軌道を外す前に勇気を持って意見を言ってください。
1.スピードが重要
慣れないことばかりやるので完成度は低くなります。大体70~80%を想定していても実際は20~30%しかできません。完成度を少しでも上げるために予定を遅らせていくときりがないので、思い切って20~30%で進みます。
しかし、職場によっては戦場のようになります。出来る人に仕事が集中するので、その人はここぞとばかり誰かに怒りをぶつける場合もあります。事前に説明しておいてもそれはあまり変わりません。怒りをぶつけられる心の準備ができるぐらいです。間違ってもいいのですぐ判断を下しましょう。
重要なのは、その場の雰囲気を感じ取ることです。スピード感を持って、繰り返し経験します。そして身体に覚え込ますのです。
2.リーダーの定義、役割を明確にする
どんどん仕事を回してどんな仕事をするのか?そんな対応がベストか?体験し、忘れないうちに記録していきます。視点の移動、視野の広がりを意識していきます。
効率を考えると、細かなマニュアルを作ってその通りにやればいいのです。OJTを考慮するとじっくり考えて試行錯誤を繰り返し、1つひとつの行動の理由を考えながら進めていきます。
そのバランスを考えながら、最終ゴールに向かうまでのマイルストンをイメージしていきます。
3.メンバーの手柄はすべて経営陣に捧げましょう
組織内に上下関係が残る限り、自分の身が安泰だったとしても競争心理は働きます。改革活動自体を業務の一環として評価の対象と捉えるのかは社長のお考え次第ですが、一番取り残されがちの役員にこそ居場所は残しておきましょう。
コアメンバーの人達は、貴重な経験をさせてもらうこと自体が褒美と考え、正当な評価以上のものを要求するのは控えましょう。
4.すぐに成果が出ると期待しない
成果が出やすいのは、別組織を新設して進める場合です。短期的に優秀なメンバーで行うプロジェクトも同様です。決めたルール通りの動きをしてくれてそこそこの成果が出ます。
ところが、その試行運用を全社に広める場合に様々な問題が出てきて予想以上に難航します。新しい組織の組み方やルール、プロセスが問題ではなく、そこにいる人達の質が問題なのです。
活動への賛否とは全く別に、頭で考えて解る人と解らない人がいます。最初から深い理解を示す人は非常に稀だと思いますが、仕事が出来る人は柔軟な思考力がありメンタルモデルの再構築ができる人が多いようです。
別組織やサンプルプロジェクトで成果を出した人の経験談を元に、全社員への意識変革の研修を組織変更と並行して行わないと期待する成果は出ません。
5.細かく分析することに意味はない
仕事ができるマネージャーのコンピテンシーや組織の力を分析することは決して無駄なことではありませんが、どうしたいかがもっと重要です。
長所を伸ばすことは出来ますが、短所を補うには、得意な人を外部から入れるしかありません。今いる人達の集合体で勝負するしかないのです。そのためには、得意なこと、出来ることで一歩でも二歩でも前に進むことです。
6.コアメンバーの行動指針を記録、更新
会社のビジョンに沿った行動指針を作ります。絵に描いた餅でなく、でも毎朝朝礼の時に読み上げる必要もなく、でも、判断に困ったり周囲の人の言動に違和感を感じたときに参照するものを作っておくと大変役に立ちます。
良い組織では、自然と周囲の人達の行動や言動から学んでいくものです。誰かの行動が何か違うなと思って近くの先輩に聞いてみると、「それもそう思う。」とか言われて反面教師的学習の機会もあり、段々揺るぎない自分の価値観となっていきます。
そういった基準を作っていくためにも、行動指針の事例は必要になってきます。
7.実務に使える行動指針をつくる
コアメンバーが作成した行動指針を元に、一般社員向けの行動指針をつくっていきます。最初は各部署ごとに使える細かな指針を書いていきます。
何度も更新を繰り返し、最終的には、社内共通と部署別のものに収束していくと思います。
8.一般社員よりで1歩先を行くために学習する
活動のメンバーは一般社員の気持ちを予測し、常に1歩先を行かないといけません。学習は2歩も3歩も先を進んでいいのですが、あまり先行しすぎると一般社員と話が通じなくなります。常に1歩先ぐらいを示し説明することを心がけましょう。
9.メンバーは周囲から洗脳されていると誤解される可能性を自覚する
学習が進み自らのメンタルモデルの再構築を行うと、もう以前には戻れません。なぜ以前はこんなことが理解できなかったのか分からなくなります。その気持ちを素直に一般社員に話すと、「アイツは洗脳されている。」と言われます。学習したことを自分から説明するのは控えましょう。
学習がもっと進むと、見える世界が変わってきますし、人の心も行動からある程度推測できるようになってきます。その能力を使って物事の先を予知したり、人の心を読んでしまうと「物事を決めつけている」と相手が急に怒りだす場合があります。なまじ的を得た指摘の場合は、人の心の琴線に触れることがあるのでなおさらです。矛盾点を追究することに熱中していると、その裏に隠されたその人のトラウマが掘り起こされるケースが意外と多いのです。
人の気持ちを思いやる気持ちはあっても、周囲から得る情報量が普通の人よりあまりにも増えてしまうと、それは憶測でも決めつけでもない事実なのです。大げさかもしれませんが、クラークケント的振る舞いが必要になってきます。
10.学んだ知識を社員にひけらかさない
メンタルモデルの再構築や傾聴のスキルは実践に使えます。というか、仕事のできる社員が持っているスキルなので役に立つのは当たり前です。請われれば説明してもいいですが、出来るだけ控えめに振る舞いましょう。
組織変更に伴う人の異動、最後は不要人員のリストラと一般社員が想像するケースが多いので、活動メンバーは少しでもマイナスの感情を持たれないようにしましょう。
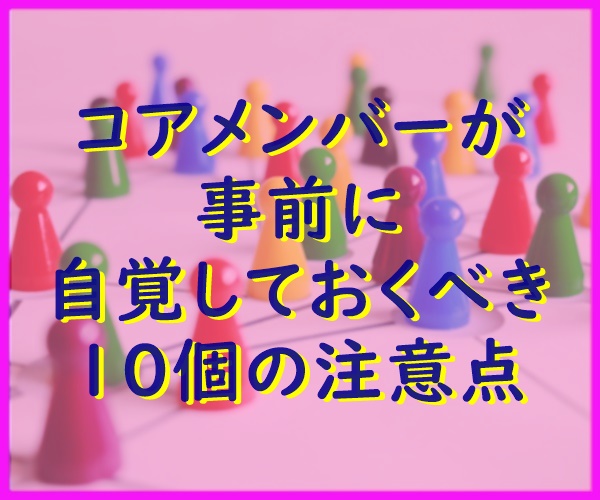


コメント