1.組織改革で最後に取り残されるのは経営陣
自分が動いた方が早いと何でも自分で決めてしまう優秀な社長の周囲には、イエスマンしか残りません。そのことに気付いたごく少数の社長さんだけが、本気で組織改革を決断されます。
社員が自立して動き出すようになるということは、社長や役員は従来のトップダウン的決断を減らしていかないといけません。以前はすべての情報を把握し、不足部分は社員に命じ集めさせ、経営陣で判断していたことを変えるのは大変な決断となります。
運良く改革が進み、権限を委譲し判断を社員に委ねていくと、経営会議で諮る必要がなくなります。そのゲートが残ったとしても、雰囲気は段々変化していきます。以前は、細かな仕様、コストや納期を担当者にプレゼンさせ、重箱の隅をつつくような質疑をして社員の自由な挑戦の芽を摘んでいた、緊張感漂う場だったのが、好々爺が若者に夢を語るような会話で和んだ雰囲気になるはずです。
つまり、社長や役員の残った仕事は、社員が働く環境を整える奉仕的業務と優れた専門性によるアドバイザー的業務だけなのです。
このことを社長は理解していても、経営陣が十分納得していない場合、クリティカルな局面で元のトップダウン的制御を行ってしまう懸念があります。もしそれを行うと、社員は権限委譲は表向きだけだったと悟り、モチベーションが大いに削がれることを御理解ください。
2.体制が変わるたびに改善プロジェクトがやり直しになる
その会社のビジョンやあるべき姿は普遍的なものであり、滅多に変わるはずのないものです。体制が変わるたびに施策が変更になることが問題ではなく、コロコロと根本から全く別のアプローチになり、社員が不信感を持っていることが問題ではないでしょうか?
ビジョンを掲げ、理想の未来像を社員と共有することを行っていれば、目先の施策が変更になっても不安や不満を感じることは少ないのではないでしょうか?
少なくとも、経営陣が真摯な姿勢で一貫性を持って取り組んでいることは、社員に伝わります。
社員の目から見て、改善プロジェクトが小手先のパッチ的対応や、社員の不満を紛らわすだけの見せかけの活動に見えていませんか?
3.要領の良い幹部に社長が騙され社員が苦労する
改革活動の発起人が社長の場合でも、実質的リーダーはその下の役員兼事業部長が担当する場合があります。
社長に対するときと社員に対するときの言動が微妙に違い、社員は全員気付いていますが誰も表立って文句を言うほどではないのでそのままプロジェクトは進行します。
そして、社員のモチベーションはいまいち上がらず、重要な局面での意思決定は従来通り、その役員兼事業部長の意見が通るシステムが暗黙の内に形成されます。表だって大きな問題を起さないから一番始末が悪いケースです。
裸の王様にならないように、社長は常に社員との意識のギャップについてアンテナを高く持ってください。
補足ですが、なぜだか分からないのですが、例に挙げた役員兼事業部長のような人は、早晩何らかの目立つ失策をして退くケースが多いようです。
4.「善人だが実力はいまいち」と「サイコパスで仕事が切れる」、どちらを選ぶ?
組織改革は、理想とする組織によって求められる人物像が変わってきます。「階層支配の度合いをどの程度残すか?」、「本社機能、スタッフ機能をどの程度残すか?」の2点を考えていき、ティール組織の成功事例とされている会社のように限界まで減らすと、現場社員自らが多くの機能を兼務することになります。
その環境で重要になってくるのは、他人と円滑に協働できるか?という点です。
他人の意見に耳を傾ける、相手に意思を伝える、ミーティングを円滑に進める等の基本的なコミュニケーション力が必須スキルになってきます。この能力は現在、世の中の多くの組織で軽視されています。チームメンバーをコーチングし共に伸びていくことよりも、強圧的リーダーシップで周囲を黙らせ従わせ、短期的成果を出す人を重宝します。
目指す組織改革で理想に近づけようとしたら、「サイコパスで仕事は切れる社員」より「善人だが実力はいまいちな社員」の方が適性があるように思います。当然、別のコンピテンシーである「責任転嫁しない」、「積極的に行動する」等も重要になってくるので安易な判断は難しいところですが、少なくとも従来の評価基準とは実務レベルで大きく変わってきます。
今まで、モラルと倫理において、無視もしくは軽視されてきた部分のコンピテンシーに光が当たります。
そのコンピテンシーがあるかどうかを社員全員で調べると、何パーセントが適性ありと診断されるのでしょうか? 従来の社員評価がごっそり変化してしまうかもしれません。
5.セクショナリズム-1;昔からのやり方に執着する部課長
真面目な部課長は、事業部全体が赤字でも、何とか自分に任された部署だけは成果を出そうとします。その結果、よく問題を起こすのが、セクショナリズムです。
自分の部署はあらかじめ決められたプロセスに忠実に稼働しようとし、他部署から飛び込みの仕事を頼んできても平気で断ります。部下から、自分達を守ってくれている、と慕われている人もいます。
社長主導の改革が始まると、自分のポジションが大きく変わる場合は別ですが、自分も部署も残れる場合は、自分の部署だけの損得に非常に敏感に反応します。
大きく組織を変える場合は、暫定的に運用して何度か段階を経て様子を見たいところですが、そういう場合にこういった部課長への対応は非常に厄介になります。目の前の緊急対応で日々根本的な問題解決から逃げていた人達ですから、改革過度期の運用への積極的feedbackも期待できません。
中には、「私が今まで築き上げてきた課がメチャクチャになった。この場合はどうすればいいんだ?」と、過度期の未完成の組織プロセスにおける、自分の部署の細かな業務の対応方法について、1つ1つ完璧な説明を要求してきます。完全に被害者意識です。
そうならないためにも、事前に十分な説明をして、協力体制を作っておかないといけませんが、必ず1人はそんなことを言う人がいます。新しい組織が落ち着いてくるまでどこまで待機して頂き、新組織の部課長として再任して頂くのか否かを判断するしかありません。
6.セクショナリズム-2;現場の改善活動
5項の真面目な部課長のように、一部の部下から慕われている管理職は環境以降時に何をすればいいのか分からないだけなのです。事前に周到な組織変更計画の概要を説明し、それぞれの部署で自分達で考えて完成度が低くてもいいので、自立してグレーゾーンを随時最適化していくことを推奨しておけばいいのかもしれませんし、柔軟な発想で業務を遂行する研修を行うのも、少しは意識改革できるかもしれません。
一般社員も同様に、意識を変えたり柔軟な発想を促す指導は、組織改革の検討と並行して進めていくべきでしょう。
一般社員が行う現場改善活動についても同じことが言えます。ほとんどの場合、自分の部署と関連する部署や顧客と連携して、できる範囲で改善活動を行いますが、根本的な個所の改善については時間がかかり後回しになってしまいがちです。改善する範囲が限定的で、発想にセクショナリズムを感じてしまいます。
自分達の現場で困っていることの原因を、もう一段視点を上げて考え直せば、改善施策も違ったものになるはずです。
7.改善活動や改革に暇な社員を任命する
バランススコアカードを使った事業戦略の運営事務局を立ち上げたり、組織改革を始めるときに任命するリーダーは有能な管理職を兼務で任命する場合が多いようです。
しかし、有能な管理職は超多忙で兼務する仕事が多すぎるため、つい「重要だが緊急でない仕事」を後回しにしがちです。そこで比較的時間が取れる社員が実働作業を行い、書類を作成して体裁を整えることが目的になってしまい、あまり意味のない活動になってしまいます。
事務局を立ち上げたら、「改善活動への適性がある優秀な社員」を期間限定で専任で任命するべきです。
改善活動は、新製品開発と同じぐらい創造性が必要な業務であり、「重要だが緊急でない仕事」のなかでも最も需要な仕事です。新入社員のOJTとしても効果的と思います。
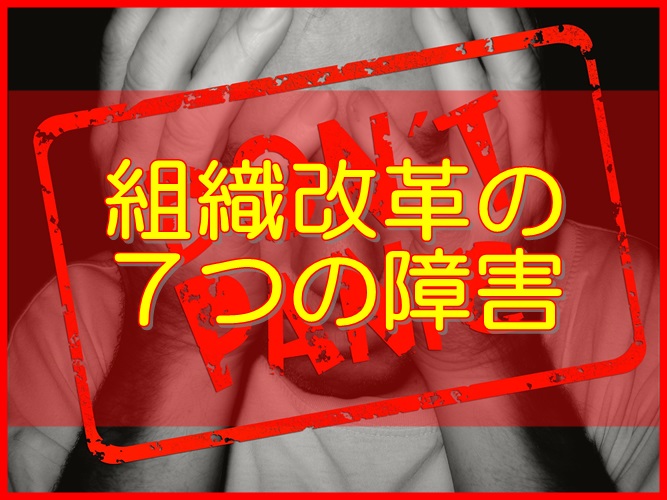


コメント